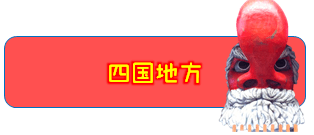私たちは、様々な言葉に包まれて生活しています。
言葉を駆使してコミュニケーションを取る私たち。
ただ、何気なく使っている言葉たちがどんな風に誕生したのか。そんなことまで考えてコミュニケーションを取ることって、なかなか無いですよね。
よくよく考えてみたら、「この言葉、なんでこんななんだろう?」って。
その言葉に出会い、由来を知りたいと思ったのも何かのご縁……なのかもしれません。
また、ご縁に誘われて言葉の起源を辿ってみると、意外と「いい言葉だな」って愛着が湧くことがあったり、それが自分の心をちょっと支えてくれる大切な友達になることもあったりしませんか?
いにしえより仏教と深くかかわってきた日本。私たちが育み、深めてきた日本語には、仏教の逸話や思想が基になっているものが数多くあります。
しかしその多くは、基になった仏教の深い意味が影を潜め、何気なく無意識に使われるだけの存在になってしまいました。
この記事では、そんな風に今では埋もれてしまった「いつもの言葉」の奥底にある本当の由来、その中でも「実は仏教由来の言葉なんだよ!」っていうものを、10個に厳選してご紹介したいと思います。
【大丈夫】

「大丈夫?」、「大丈夫!」。
たった3文字ながら、問いかけても応えても、人を思いやる心を表す素敵な言葉です。
“All right”である状態、自分や相手が最大級に「丈夫」である状態を示すこの言葉ですが、では「丈夫」って、なんで「丈夫」って言うんでしょうか。
「丈夫」とは、「健康」で「頑丈」なさまを表す言葉として使われています。また「夫」ですから、特に昔の日本では強く堂々とした男性、「益荒男(ますらお)」を指して言われていたようです。
しかし漢字の母国である中国では、「丈夫」な男性を満たす条件は強く堂々としているだけでは足りず、豊富な知識や人望も兼ね備えた、まさに“All
right”な人でなければ「丈夫」と称されることはなかったようです。
心身ともに健康堅固で、なおかつ才覚や人徳にも満ちた存在。
「そんな人間はいないよ。仏様かな?」
昔の中国の人々はそのように考え、「丈夫」に「大」までつけて、仏様を敬いました。

このように、「大丈夫」とは、万能で人々の憧れる仏様を称する別名のひとつでした。
「大丈夫」という言葉が仏様のことだと知ると、いつものようにこの言葉を使っていた私としては「いやいや、私はそんな器じゃございません…」と恐縮してしまいますが、他人にも自分にも「大丈夫」と言い聞かせ、行先が“All
right”であることを願えば、仏様のご縁で何か良いことがあるかも…。そう思えば、「だ、大丈夫…(汗)」と無理しなくてもよくなるかもしれません。
【勝利】

スポーツも勉学も経済も、競争に興じた「昭和」を経て、「平成」も終わりに近づくこの頃では競争社会に疲れてしまった人も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

当然ですが、競争に「勝つ」こと、「勝利」とは相手を打ち負かすことで成り立つものです。生き物は弱肉強食の世の中で、相手を打ち負かすことで生き残ろうとしますが、人は何かを打ち負かすことによってお金や名誉や喜びを得ようとします。そしてそれを生きるための力に変えることで、新しい勝利につなげていこうとします。
俗世の競争社会とは一見無縁そうな仏教の教えの中にも、意外なことに「勝利」という言葉があります。他人と競うことなど真っ先に「やめておきなさい」と言いそうな仏教でも「勝利」という言葉が使われるとは…戸惑いを隠せない方も多いのではないでしょうか。
ただし、仏教で用いられる「勝利」という言葉には、私たちが日常で使う「勝利」には必ずつきまとうものがありません。それが「敗北」です。

私たちの常識では、「勝利」には、その裏に「敗北」が控えています。
人は勝利を目がけて競い合います。戦いの果てにたとえ勝利を得たとしても、安心してはいられません。一度は敗北を味わった者が勝利を機会を虎視眈々と狙っていることもあり、せっかく得た勝利を奪われる心配に常に苛まれます。
人の世で獲得する勝利とは、いつでも失う恐れのある、誰にとっても無常なものなのかもしれません。
しかし仏教の「勝利」は、一度得られれば失うことはありません。
「勝利」を仏教の言葉として訳すと、「勝」は「優れていること」、「利」は「ご利益(ごりやく)」となります。ご利益とは、仏教では「仏様の恵みを授かること」。仏様の恵みとは、ざっくり言えば「悟り」です。悟りはレースではないので、自分だけが授かるということもなければ、一度到達すれば失うことも奪われることもありません。仏教では、優れた悟りを授かることが「勝利」なんですね。
ご利益(ごりやく)は、読み方ひとつで利益(りえき)とも読めます。
利益(りえき)には、絶えず大小や損得などの「ポジティヴ/ネガティヴ」の感覚がつきまといます。そして、利益(りえき)を強く追い求めると、少しでも多く、少しでも得を、と絶えずハラハラしながら生き続けることになります。
しかしご利益(ごりやく)には、むしろそのようなハラハラから脱するために授かるものです。仏教の意味での「勝利」を掴むことができた人は、失われることのない本当に大切なものだけを手に、とても穏やかな心持ちで居られるのでしょう。
【うろうろ】

不安な時。居ても立っても居られない時。心の中に良かれ悪しかれ何かが芽生え、湧き起こり、じっとしていられず右往左往してしまう。
人の心理として仕方のない状況を表して、「うろうろ」すると言います。
この「うろうろ」とは、浮き足立ってあちこち歩き回ってしまう状況の擬態語(オノマトペ)だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

しかし、この「うろうろ」は漢字で書くと「有漏有漏」。つまり擬態語ではなくちゃんとした意味を備えた言葉だったのです。
この「有漏」とは仏教の言葉で、そのままの意味では「漏れ出るもの」です。
では、この「漏れ出るもの」の正体は何なのでしょうか。
仏教によれば、この「漏れ出るもの」は人の目や鼻や耳といった感覚器官から漏れ出て心を乱すとされています。
好みのタイプの人を見かけたり、美味しそうな料理の香りを嗅いだり、…人はそのような感覚器官から何気なく得た情報を、知らず知らずのうちに欲求に替えています。これは仏教で言う「煩悩」です。
ですから「漏れ出るもの」とは、感覚器官から漏れ出し心を乱すもの、つまり「煩悩」のことなのです。
心乱されてじっとしていられない時、私たちの中には「煩悩」、つまり「有漏」のものがたくさん流れ出していて、それ故に「有漏有漏(うろうろ)」してしまう。これがこの言葉の起源なのですね。
昔、とあるお坊さんにこんなことを聞いたことがあります。
「有漏」のものは、たとえ手にしたとしてもいずれ漏れ出ていってしまうものです。
私たちはお釈迦様の教えを頼りに、「無漏」の法、つまり一度手にすることができたら決して漏れ出ることのない「悟り」を得るために、この世に生を受けているのです。
自分の中から決して失われないもの、それは自分の手で生み出さなければならなさそうですね。
【邪魔】

「邪魔」。一見おぞましい字面のこの言葉。
実は仏教が産んだ言葉なのです。
「邪」は「よくないこと」、「魔」はインドの古い言葉、サンスクリット語で「マーラ」という魔神のこと。
言い伝えによれば、お釈迦様は悟りに至るべく瞑想を始めた時に、魔神マーラがやってきてお釈迦様に煩悩を生じさせようと数々の妨害を繰り出しました。綺麗な女の人たちを送り込んだり、岩を降らせたり、怪物に襲わせたり…
でもことごとく失敗してしまいました。お釈迦様の煩悩を乗り越えようとする力が優ったのです。これによってマーラは自分の負けを認め、お釈迦様はめでたく悟りを開かれたということです。
この逸話はお釈迦様vs.マーラの対決として描かれています。
しかし、この対決が繰り広げられているのはお釈迦様の頭の中、つまり魔神マーラはまだ悟りに至っていないお釈迦様自身の煩悩そのものだと言われているのです。お釈迦様が戦ったマーラ、つまり「邪魔」は、自分自身の中に沸き起こったものだったものだったのですね。

私たちが日々「邪魔だなぁ」と感じること、それは常に自分の外側から自分を妨害してくるように思いがちです。しかし現に「邪魔だ」と思うのは自分自身の心なのであり、心がそう思わなければ、世の中に「邪魔者」などいないのかもしれません。
またここには、人が抱きがちな「邪魔だなぁ」という何気無い感覚には、それが知らず知らずのうちに溜まってストレスになったり、大きく膨らんでいけば人々を翻弄する憎悪につながってしまう危険も孕んでいます。
人が「邪魔」なものとそうでないものを分ける時、無意識のうちに物事の「良し悪し」をもって判断しています。「良し悪し」は単にその時の利害に基づくこともあれば、その人その人がそれまで生きた文化や人生経験の中で培われてきた軸によって判断されることもあります。したがって、それらの基準による「良し悪し」は、それを決めている人の「都合」の域を出ないものではないか、と仏教は問いかけています。
私たちが「邪魔」と感じてつい悪く言ってしまうのは、私たちにとって「都合が悪い」からなのであって、無意識のうちに「邪魔」のレッテルを貼っているからなのではないだろうか。本当は「邪魔」なものなど一つもなく、ただ存在しているだけなのではないか。…と。
自分にとって「都合の悪いもの」を、自分で決めた「絶対に正しい良し悪し」に落とし込んでしまい、知らないうちに「敵と味方」を分けてしまう。それがどんどん大きくなると…結構恐ろしいことが想像できてしまいますね。
この逸話には「邪魔」が育って取り返しがつかなくなることを防ぐための教訓も隠されているのですね。
「邪魔」なものは常に自分の心で決めている。それを念頭に置いて心を安寧に導くことは、忙しさに追われる社会ではなかなか難しいことです。でももし自分が「邪魔」にしているものを、お釈迦様のようにストンと腹の中に落とし込むことができれば、心がスパッと晴れるのかもしれませんね。
【ほーほけきょ】

寒さが少しずつ和らぎ、梅のつぼみがほころぶ頃、春を告げる声が野山から聞こえてきます。
ほー ほけきょ
日本の春だなぁとしみじみ思う情景です。
うぐいすは今も昔も日本人にとっても親しみのある鳥で、とても可愛がられてきました。「ほーほけきょ」の鳴き声は、聴いた人に春の暖かさを運んでくれる嬉しい知らせ。古来、この鳥が「春告鳥」と呼ばれていたこともうなづけます。

さて、この「ほーほけきょ」といううぐいすの鳴き声が、仏教の言葉を指していることはご存知ですか?察しのよろしい方はお分かりだと思いますが、仏教のお経の中で「諸経の王」と称される「法華経(ほけきょう)」のことなのです。たまたま鳴き声がお経の名前の様に聴こえるというだけなのですが、うぐいすはありがたいお経の名前を呼び続けることで功徳を積んでいるのでしょうか。
法華経。
恐らく多くの方が名前だけでも聞いたことがあるのではないでしょうか。
法華経というのは略称で、正しい名前を「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」と言います。
法華経はさまざまな宗派で幅広く重んじられ、また読み物としても昔から大変人気があり、仏教徒ではない人々にも読まれています。
その理由は、お釈迦様が目指した「誰でも平等に悟りを開くことができるように」という願いが体現されていること、そしてそれを説くためのストーリーが巧みであることでしょう。
法華経は全28章から成る長いお経で、大きく前半と後半に分けられます。
前半には、悟りを開くための方法は1つではなく、大きく3つあること。
後半には、悟りを開いて仏様に成るのはお釈迦様だけではなく、誰もが悟りの道へ導かれることが、
お釈迦様のもとに多くのお弟子さん、お釈迦様の奥さんやお子さん、そしてインドの神々が大集合しているところで、それらの登場人物が代わる代わるお釈迦様と問答を繰り返していくスタイルで説かれていきます。
詳細な内容は別に機会に譲りますが、お坊さんでなくても、まして仏教徒でなくても、誰もが平等に悟りを開くことができる。階級社会真っ只中の当時にそんな画期的な提言をしているのですが、お釈迦様やお弟子さんたちが繰り出す面白いたとえ話や昔話、そして登場人物たちの目の前でお釈迦様やその他の如来様が巻き起こす“スペクタクル”によって、臨場感たっぷりに描かれています。
法華経は、仏教という宗教の形式ではなく「悟り」そのものを大切にしているという点で、本当に「誰に対しても開かれた」教えなのだなと思います。またいつかお話しできる機会があればと思います。
うぐいすが法華経のお話にいざなってくれました。ところで、私には疑問が残ります。
うぐいすは、どうして「うぐいす」って言うのでしょうか?
正解は、鳴き声です。
え?と思いますよね、「ほーほけきょ」じゃないの?って。
実はうぐいすの鳴き声は、昔は今とは全然違う言い表し方をされていたのです。
うぐいすとその鳴き声は古くは平安時代から親しまれていたようですが、その鳴き声が「ほーほけきょ」と言い表されるようになったのは、実は江戸時代。結構最近のことなのですね。
そして、「ほーほけきょ」になる前は「うくい」と表されていたのだとか。
古語では「う」は今の「ふ」に近い発音に、「い」は今の「ひ」に近い発音だったと言われています。ですから、平安時代の人々がうぐいすの鳴き声を表す時には「ふくひ」と言っていたのでしょう。
「ふー くひっ」っていう感じでしょうか。これなら現代人の私たちにもわかるような気がします。
この鳴き声に「鳥」を表す古語、「す」をつけて「うくいす」。それが訛って「うぐいす」になったというのが、この鳥の名前の由来なのだそうです。
昔の人々も、この鳥の声で春の訪れを知っていたと聞くと、「変わらないこと」もいいもんだなと、「諸行無常」を説く仏教について書きながらも思うものです。
【会釈】

見たことはあるけど話したことのない人、直接知らないけど社内ですれ違う目上の人、親しくなりたいけどどこか話しかけづらい人。
積極的に挨拶するのははばかられたり、お辞儀をするほど改まった場面でもない…そんな恥ずかしがり屋な日本人に必要なコミュニケーションツールが「会釈」ではないでしょうか。
挨拶と無言、お辞儀と知らんぷりの間を器用に埋めてくれる「会釈」。実はこれも仏教由来の言葉だったことをご存知ですか?
会釈の起源は、仏教の言葉である「和会通釈(わえつうしゃく)」です。
和会通釈とは、一見全く相容れなさそうな教義や主張同士をじっくりと眺め、お互いの共通点を探し出すことによって、実はその根本は通じ合っているのだと読み解くことです。そしてこの四字熟語を略して「会通」とか「会釈」と呼び、会釈が今日まで日常語として残っているというわけです。

元の意味を辿ると、現在私たちが使っている軽いコミュニケーションツールとしての会釈とはかなり隔たりがあるように思います。
しかし、こう考えてみたらどうでしょう。
そもそもコミュニケーションとは、私目線では自分の存在を相手に示すことです。しかし相手第一の目線に立てば、その時に会ったその人がどんな気持ちなのかを推し量ることでもあると思います。相手の気持ちは元よりパッと見ではなかなか分かりにくいもので、「どんな気持ちなのかな」と思いやることでだんだん見えてくるものです。それは「和会通釈」の意味するところに近いのではないでしょうか。
「自分とは異なるかもしれない、真意の見えない相手を思いやる」ことが「会釈」の根本なのかもしれませんね。
また、「和会通釈」はたとえ反りの合わない教義でも、根本にある共通点をお互いに理解すれば仲良く同居することができることも意味していると説明しましたが、私たちが日常何気無くしている「会釈」も同じようなところがあります。
あまり親しくないけれども、その人を思いやって軽いコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、その2人の関係を近めたり、円滑にしたり、潤いを与えたりする。何気ない日常の一コマであっても、人間関係を少しずつ豊かにしていくという意味で相通じるところがあるのかもしれません。
そして、コミュニケーションに「会釈」を取り入れているのは、日本人や仏教徒だけではありません。会釈を軽く頭を下げることに限定しなければ、世界には通りすがる知らない人に対しても、微笑みかけたり、ウィンクをしたり、いろいろな何気ないコミュニケーションツールがあります。
「会釈」が自然に備えている思いやり。相手に「今日一日、良い日でありますように」と慮る気持ち。それは、世界共通の思いなのかもしれませんね。
【機嫌】

他人の気分を伺う時。他人の虫の居所を窺う時。
私たちが気にする他人の「ご機嫌」という言葉は、「伺う」という字も「窺う」という字も使い、ポジティヴにもネガティヴにもお世話になっている言葉です。

機嫌の「機」は、実は昔は「譏」という字を使っていました。「譏」は「譏る(そしる)」という意味、つまり「他人のことを悪く言う」ことです。したがって、昔使われていた「譏嫌」とは、他人の嫌なところを譏るという、完全にネガティヴな言葉として使われていたことになります。
そして、これこそ仏教で使われる「譏嫌」なのです。
仏教に人生を捧げるお坊さんは、そもそも経済活動をしないことになっています。したがって彼ら彼女らが生活していくために必要な衣食住は、在家の人々の「お布施」で成り立っています。「布施」とは仏教においては悟りの世界に至るための6つの実践(六波羅蜜)のうちのひとつです。布施には3種類あるとされ、お金や品物の寄付はそのうちのひとつに過ぎません。残りは仏様の教えを説くことと、何かに恐れ慄いている人々を慰めて恐怖心を取り除くことです。後者2つはお坊さんでなければなかなか難しい行いなので、主に在家の人々にできるのがお金や品物の寄付を以っての布施となるわけです。
信仰の篤い在家の人々は、自分達には及ばない残り2つの布施をお坊さんに代わりにしてもらうため、昔からこのお布施を続けてきました。それによってお坊さんたちの生活は成り立っていたわけです。
しかしながら、他人に生活を委ねているお坊さんが贅沢三昧に浸っていたり、目を疑うような自堕落な生活をしていたら、在家の人々はどう思うでしょうか。在家の人々からの布施が滞りお坊さんは生活できなくなりますし、お坊さんにしかできない他2種類の布施を託していた在家の人々も功徳を積むことができなくなってしまいます。これでは出家者も在家者も共倒れになってしまいますね。
そこで、お坊さんたちは自分たちの生活に厳しい戒律を設け、在家の人々の理解を得るようにしました。その戒律が「譏嫌戒(きげんかい)」というものです。お酒を飲まないとか、ニンニクやタマネギなど臭いの強いものは食べないとか、法的には全く罪に問われないことでも、在家の人々から「譏り嫌われない」ようにするため、お坊さんの行動を詳しく規定しているのですね。
もちろん、在家の人々に後ろ指を指されないためだけにこのような禁止規定を設けているわけではありません。実際に、お酒はもちろん、臭いの強い食べ物やスパイス、お肉などの食材は食べることによって力も湧きますが、精神が高ぶった状態になるので仏道修行には向かないという側面もあります。
ちなみに譏嫌戒で禁止されているニンニクやネギ、タマネギなどの臭いの強い食材を昔は「なまぐさ」と呼んでいました。今日でもお坊さんに悪い評価をする際に「なまぐさ坊主」と呼ぶのは、まさにそのお坊さんが在家の人々から「譏り嫌われる」ことをしてしまったということなのでしょう。
他人から譏り嫌われないように努力することは大切です。
しかし、それを第一にしていても、いつも肩に力が入っているようで窮屈な気もします。
嫌われないようにする努力も好かれる努力も、両方をこなすことができて初めて一人前のお坊さんということなのでしょうか。なんだか、果てしない修行が必要なようですね…
【愛】

とてもピュアな印象を与えるこの言葉は、その印象ゆえに様々な場面で使われます。
誰かを大切に思ったりすることも「愛」。彼・彼女に近づきたいと思う気持ちも「愛」。面識はなくても出身校や同郷の選手を応援する情熱も「愛」。地球を救うとされているのも「愛」。
人間が持ちうるとても万能な力のひとつとも言えるかもしれません。
しかし、この「愛」という言葉。日本でこのような使われ方をされるようになったのはつい最近、明治時代になってから。つまり“Love”という言葉が輸入されてからだと言われています。
もともと「愛」という言葉は日本にもありました。しかし“Love”という言葉の持つポジティヴなイメージとは真逆の意味を持つ言葉だったのです。

「愛」という言葉を日本に初めて持ち込んだのは、弘法大師・空海だと言われています。
彼は中国で仏教、特に密教を学んだ際に「愛染明王(あいぜんみょうおう)」という仏様に出会います(愛染明王についてはこちらのページをご覧ください)。
意外かもしれませんが、仏教において「愛」は煩悩のひとつであり、人を救うどころか苦しみのうちのひとつとしてカウントされています。お釈迦様は、人が持つ8つの苦しみ(八苦)の中に「愛」を入れています。人を愛することは執着を生み、やがて訪れる愛する人との別れは愛がもたらす最大の苦であると言うのです。
しかしこの愛染明王は、仏教で排除すべきものとされている煩悩、それも苦の代表格である愛やドロドロとした愛欲までも一旦は受け入れてしまう仏様です。そして、そういった愛をめぐる苦しみをも、悟りへ向かう力に変えてしまうというお役目を持っていらっしゃるのです。
こうして見ると、つい最近まで日本の人々は「愛」とは厄介なものだと思っていたようですね。よく考えてみれば、確かに「愛」は執着に変わりがちで、裏切られた時の悲しさや思い通りにいかなかった時の憤りは、「愛」を持って接すれば接するほど強烈になることもあります。また、“Love”の意味を持つ「愛」も、自分の好きなように愛を振りまくことを説いているわけではないようにも思います。
他人への「愛」は自分の執着というフィルターを通すのではなく、他人の目線、他人の感覚、そして他人の「愛」をも大切にすることによって果たされることなのかもしれませんね。
【上品・下品】

数年前に流行った言葉に「品格」という言葉があります。
「国家の品格」で人気に火がつき、「紳士の品格」に「女性の品格」、「シニアの品格」やら「ハケンの品格」などなど。誰が決めたかも分からない基準によって人のいろいろな素性の「品格」が決められ、自分がその品格を満たしているかを気にするという一種の社会現象。本やテレビやネットが出題する「あるべき人間」としての抜き打ちテストのような感覚を憶えています。

自分が果たして示された条件をクリアした「品格」を備えた人間なのか。人からの印象を少しでも良くするためには、部下に慕われる上司になるためには、女の子や男の子にモテるためには、自分には何が足りないのか。「品格」が広く認識され、ダメ認定されないように自分を「高める」。そんな自己啓発の側面もあったかもしれません。
「品格」は、今では人として備えるべき品位に格差をつけたもので、明確な基準は無かったとしても、その人が持つ礼儀や節度、人徳や気高さなどを総合して他の人から何気なく認定されるものです。人は人間同士で「あの人は上品/下品だ」とランク付けし合っているのです。
しかしこの「品(ひん)」、特に「上品」、「下品」は元は仏教の言葉で、しかも「上品/下品」の判断はそもそも人が決めるものではなく、仏様が決めるものなのです。
また、仏教では「上品/下品」を「じょうひん/げひん」ではなく、「じょうぼん/げぼん」と読みます。「品」を「ほん」または「ぼん」と読むのですね。
先程、人の「上品/下品」は仏様が決めると言いましたが、人のどんなところが決め手になるのでしょうか。
人間の社会では「上品/下品」はその人の見た目や態度、所作など、外見を基にして判断されます。しかし仏様の見定める「上品/下品」は外見ではなく内面です。
ここで言う人の内面とは、その人が心に積み重ねた善悪のこと。つまり、この世を生きている間にどれほどの功徳を積んだかということが決め手になるのです。
仏様は人の内面を見定めて、「九品(くほん)」という独自の分け方をしていき、そして人々をそれ相応の極楽への往生の導き方を決めます。
「九品」には、先程から登場している「上品」と「下品」の他に「中品」があり、さらにそれぞれの「品」の中を3つに分け、「上の中」や「中の下」などのように全部で9つに分類していくのです。また、「品(ぼん)」の下位は「生(しょう)」と言います。
したがって仏様は人々を極楽に導く際に、私たちを生前の功徳に応じて
「上品上生、上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生」
という9つに分け、それぞれに合った導き方をするというのです。

ちなみに、九品それぞれに沿って導いてくださる阿弥陀如来を9体のお姿で表した「九品仏(くほんぶつ)」は、東京・世田谷の九品仏浄真寺や京都府・南山城にある浄瑠璃寺にお祀りされています。お堂に入ると、9体の阿弥陀様が並んで迎えてくださいます。阿弥陀様はそれぞれに手に結ぶ印相が違っていて、それぞれが異なる方法で私たちを導いてくださることを表しています。
.
もちろん、最大限に善い行いを続けていれば「上品上生」、悪行を積み重ねれば「下品下生」と分類されるわけですが、大切なのは仏様は全ての人を阿弥陀如来の司る極楽浄土に導こうをされることです。
上品上生の人は極楽浄土へ行くまでの道のりが短くて済むということには違いないのですが、悪行を続けた人も、仏様がそれぞれに出す課題をクリアすることによって極楽浄土行きの切符を手にすることができるというわけです。
その意味で仏教の「品(ぼん)」は、人をランク付けして褒めたり貶したりする目的ではなく、極楽浄土へ行くための学びを得るためにその人の能力に応じて事前に教え込むための教室分けのようなものなのかもしれません。
善を積み重ねた人はもちろん、悪を重ねた人も極楽往生できる。
「品」とは人の社会において人を格付けするための言葉ではなく、仏教の優しく大らかな姿勢を反映した言葉だったのですね。
【安心】

この世は不確実なことばかり。
いつ危ない目に合うか分からない。いつ不利益を被るか分からない。いつ信頼を失うか分からない。
私たちは日常に溢れている様々なリスクに対処する、つまりリスクヘッジすることによって「安心」を得ようとします。「備えあれば憂いなし」という意味合いが強いですね。
しかし、仏教用語としての「安心」はリスクに恐怖して備えを万全にするというよりは、諸々のリスクを「恐れない」という意味が強いように思います。
人は煩悩を抱えているからこそ「自分にとって都合の悪いこと」が生じるわけで、それを予想しても、予想が現実になっても、恐れや怒りや嘆きが引き起こされる。だから、煩悩を捨ててしまえば次々と思い浮かぶリスクに戦々恐々とする必要もなくなるのだと、仏教は唱えているのです。
とても単純な論理ではありますが、そのような「悟りの境地」へ行き着くのはとても大変ですよね。
ただ、見方を変えると「安心」の別の側面が現れてきます。
人が心配するのは前途に「不確実」なことがたくさん待ち受けていて、それに遭遇すると自分自身がどうなってしまうかも「不確実」であるから心配が尽きない。
だから自分自身が「確かな存在」になれば、「不確実」なことへの心配は消えていく。
仏教は「安心」という言葉を通して、そのように伝えています。
仏教で「安心」という言葉を初めて使ったのは、「達磨大師(だるまだいし)」というお坊さんです。

達磨大師とは、あのまん丸な人形のダルマさんのモデルになった南インド出身の禅僧で、高齢にも関わらず禅を広めるため中国まで旅を続けました。それによって禅は中国に定着し、やがては日本にも臨済宗や曹洞宗が誕生しました。
ちなみに、人形のダルマさんには手足がありませんが、ホンモノの達磨大師にはちゃんと手足はあったようですので「ご安心」ください。これは一説によると、座禅のし過ぎで達磨大師の手足が腐ってしまったという伝説に由来しているそうです。なかなかエグい伝説だとは思いますが…
さて、達磨大師の説く禅は、「壁のように動ぜぬ境地で真実を観ずる禅」と言われています。彼は中国を訪れた際、中国で以前から儒教で説かれていた「天命に身を委ねて心を平安に保つ」という意味の「安心立命(あんじんりゅうみょう)」という言葉に出会いました。そこで彼は、自身の禅に対する眼差しをその四字熟語に重ね合わせ、そこから2文字を借りて、「安心」という言葉で表現しました。これが日本にも伝わり、今日でも私たちが日々使っている言葉になっているのです。

お金や健康や地位など、人が求めがちな「安心」の源は価値が乱高下しがちです。そういった変化しやすい「リスクを抱えた幸福感」をものさしにして自分を推し測るのではなく、「どのような状態、どのような環境も、すべて自分なのだ」という受け入れの意識を持てば、壁のように動じない「確かな」自分を作ることができる。「確かなもの」さえ持つことができれば、「不確実」なリスクへの恐怖は消えていく。その道筋を進むために、仏教がアドバイスしてくれていると思うところがあるのです。
「確かなもの」を得た時、人は本当の「安心」を手に入れることができるのかもしれません。
以上、実は仏教の言葉だった!という言葉を10個あつめてみました。これ以外にもみなさんの身の回りや普段発している言葉のなかには仏教に関連した言葉たちはあふれています。
仏教という言葉を聞くと、自分には関係がないと感じてしまうかもしれませんが日本人にとって驚くほどに生活に溶け込んでいるのが仏教です。ウォーリーをさがせ!のようにみなさんも我々の身近に溶け込んだ仏教を探すのは意外に楽しいかもしれませんね。
.