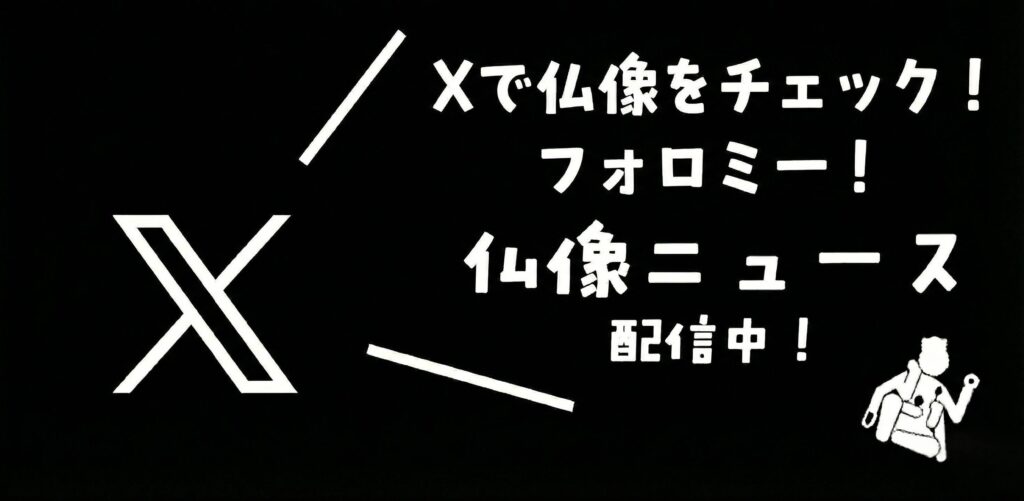【見仏入門】No.30 兵庫・浄土寺の仏像・見どころ/国宝浄土堂阿弥陀三尊像(快慶作)、薬師如来像など

浄土寺は兵庫県小野市にある鎌倉時代に東大寺を再興した重源が建てたお寺です。ここは仏像ファンならずとも知ってるという人は多いかもしれません。ここは建築と自然が合体し神秘の姿を見ることができるスポットとして幅広く観光客が訪ねています。
浄土寺の神秘の秘密はなんてったって浄土世界を体感できてしまうのです!ただし期間・時間限定なので注意くださいね。
その体験の主人公は阿弥陀さま。5m以上(須弥壇を含めると7m以上)もある阿弥陀如来像が中尊として立っていて、両脇の脇侍も高さは4m近くあるため、まずこの大きさに圧倒されること間違いなし。像から離れた壁際でゆっくり座って夕日が堂内にあふれる時間を待ちましょう!きっと新たな仏像の世界に皆さんを連れて行ってくれると思いますよ!さて、今回はそんな浄土寺の見どころのご紹介。みんなで浄土の世界をのぞいてみましょう?!
It’s a beautiful day.
兵庫県小野市にある浄土寺に行ってきました。阿弥陀如来像かなり迫力あって綺麗でした! #浄土寺 #小野 #temple https://t.co/STF6UGvJH9 pic.twitter.com/ALAVfsq9NP— D_Drive Yuki (@D_Drive_Yuki) 2017年1月3日
【夕暮れ、浄土堂ショー】
新年アンコール放送で楽しんだ NHK Eテレ『びじゅチューン』。仏像好きの間で話題になったこの作品は、日々、鍛練を重ねた阿弥陀三尊のオンステージで、カラオケバーで聞く歌謡曲風whttps://t.co/sVa7jsKRoA#仏像 #butsuzo #浄土寺 pic.twitter.com/9o0SKnNGM9— Takaタカ (@vietnamcat) 2019年1月7日
浄土寺の見どころ
浄土宗の考え方では西の太陽が沈む西のかなた先に極楽浄土の世界(西方浄土:さいほうじょうど)があり、そこには阿弥陀如来がいて信者が死を迎えた時、極楽浄土の世界から阿弥陀仏が迎えにやってくる(来迎:らいごう)と信じられていました。

この浄土寺はこの来迎の世界を感じることができる場所だといわれています。それもあの有名な仏師快慶の大きな阿弥陀三尊が光り輝きながら極楽浄土から迎えに来るのです。
鎌倉時代に重源の建てた真四角の浄土堂は今も残されており、そこには有名な仏師快慶が制作した大きな阿弥陀三尊像が安置されています。お堂も内部の仏像も共に国宝に登録されています。
そしてなんといってもこの三尊を拝観するのはお堂に西日が強く当たる時季と時間を選んで訪問されることをお勧めします。

なぜなら、浄土堂の壁は蔀戸(しとみど)になっていて、壁の一部の格子が上に吊り上げられる構造になっています。夕日が差し込んでくると足元は雲のようにかすんで見えてきて、まるで阿弥陀如来が雲に乗って迎えに来るような姿として現れます。
また夕日がお堂の中に差し込まれ、像の後光として輝くとともに堂内の壁や床に反射した光を受けて金色に輝く阿弥陀如来様が赤く光り輝きます。
まるで夕日の色と光がこの金色の大きな阿弥陀三尊を包み、足元は雲のようにかすんで見えてきて、まるで西方浄土から阿弥陀如来様が雲に乗って現世に迎えに来るように見えます。いわゆる来迎(らいごう)の世界を現したものです。
この来迎の考え方は、死者をあの世の極楽に連れて行ってくれるということなのですが、現世で生きる者には、そこで生きる希望や力を与えてくれるのだと気がつくのではないでしょうか。

浄土寺へのアクセス

浄土寺へは神戸電鉄粟生線の電鉄小野駅からバスで約10分ですが、コミュニティバス(らんらんバス)がいろいろなルートで走っていますが、浄土寺前に停まるバスは1日に2本くらいしかありません。歩くと50分くらいかかりますので、近くの他のバス停(浄谷〈きよたに〉、坂下など)を通るバスを探さなければなりません。私は昔歩いていったことがありますが、距離はかなりありましたが、平らな道なのでそこまで苦労せず到着できました。
駅前にはタクシーがありますので、いざとなればタクシーをご利用ください。車の場合は、山陽自動車道の三木・小野インターから約15分で到着します。近くでレンタカーを借りて訪れる方も多いようです。
小野駅で時間が余ってしまったら駅から西に3分くらいの所に「小野市好古館」という施設(月曜日休館)があり、小野市や浄土寺の歴史などの紹介もありますので見学されていくのも良いでしょう。
東側にある薬師堂の裏山には、初夏に約1万本のあじさいが咲きます。またそこには四国八十八ヶ所めぐりができる林道があり、江戸時代に建てられた祠なども点在しています。
浄土堂の拝観時間は、朝は9時からですが夕方は4月~9月が5時まで、10月~3月までは4時までです。また浄土堂は12時から1時まで昼休みで拝観できません。
浄土寺の来迎を体験できるのは、いつ?
ここを訪れるのが、来迎を体感できる夕日が堂に当たる時間となると、この訪問する時期はやはり重要ですので、少し調べてみました。
小野市の日没時間は最も遅い6月の夏至では19時18分頃、最も早い12月の冬至では16時54分頃となっています。4月~9月では夕方5時で閉まってしまうのでこの閉館時間の5時と日没までの差は、
・4月1日で約1時間20分
・夏至(6月):約2時間18分前
・9月30日:約45分
10月~3月では夕方4時で閉まって
・10月1日:約1時間45分
・冬至(12月):約54分
・3月31日:約2時間20分
となります。結果は9月末か12月の冬至の頃になるのでしょうか。
また天気が良くなければ意味がありませんので、この季節でも天気の良い日に行く必要があります。なかなかタイミングは難しいかもしれませんね。
ただ夏場の7月~8月頃でも午後2時過ぎになれば西日が差し込むといわれていますのでこの夕刻の頃でもよいかもしれません。
また寺の立地は、東側は丘陵の尾根の先端の少し小高い丘陵に建っています。
そのため西側が開けており、ここから夕日が望めますので、西方浄土が実感できる場所に寺を建てたといえます。

浄土寺の駐車場
国道2号線を明石より国道175号線に入り小野にて右折、東条線を数分。約30台、大型バスも駐車可能な無料駐車場があります。
浄土寺の歴史
浄土寺は鎌倉時代のはじめ、奈良東大寺を再興した重源(ちょうげん)上人が建立した寺院です。奈良東大寺が1180年に平重衡(たいらのしげひら)による南都焼討によって大打撃を受ける事件が起こりました。この時、東大寺の大仏および大仏殿が焼けてしまったのです。

この東大寺の復興に指名されたのが重源上人です。 上人は、まずこの復興を後押しする拠点となる7か所の寺(東大寺別所)を東大寺周辺の各地に置きました。播磨別所、周防別所、伊賀別所、東大寺別所、高野別所、渡辺別所、備中別所の7か所です。播磨別所がこの浄土寺です。

この播磨別所の場所は東大寺領であった「播磨国(はりまこく:今の兵庫県)大部荘(おおべのしょう)」という荘園がありました。
この地域は、もともと東大寺の大仏を建立した時に総指揮を執ったといわれている行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が東大寺の建設時にやはりこの近くに寺院を立てたといわれていて、奈良時代中期の8世紀に現在の浄土寺の西側2kmほどの場所に「広渡寺」という寺が建てられていたと伝わっています。
重源上人も新しく寺を建てたというよりもこの広渡寺を復興したと考えていたのかもしれません。この広渡寺は現在ありませんが、「広渡廃寺跡歴史公園」として基壇(建物の基礎)などが復元整備されています。またこの広渡廃寺は奈良の薬師寺と同じ伽藍配置であったといわれています。

播磨別所の建設は、1190年にこの東大寺再興料所として大部荘(おおべのしょう)という荘園を受領できたことによります。まずその建設目的は復興資金の調達があげられますが、それ以上に建設用の木材の調達が大きな役割だったと思われます。

地理的には加古川と瀬戸内海を結ぶ水運の便が良く、木材などの物資の調達や運搬の拠点にとても良い立地だったということが決め手だったと考えられます。
また、重源は寺の敷地の中央に極楽浄土式の池を置き、西に浄土堂、東に薬師堂を、池を間に挟んで向かい合うように配しました。これは、西方浄土の阿弥陀如来の世界と、東方浄瑠璃世界の救世主である薬師如来の世界を表しています。
そして浄土堂には仏師快慶が製作した大きな阿弥陀三尊像を祀り、薬師堂には薬師如来を祀ったのです。
この浄土寺の建設は1194年に始まり1197年に完成したとされています。現在の浄土堂はこの当時の建造物ですが、薬師堂は火災にあい室町時代の1517年に再建されたものです。
またこの2つのお堂の中央脇に1235年に本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)に基づいて配された鎮守社である「八幡神社」が置かれ、現在の建物は室町時代中期に再建されたものです。

本地垂迹説というのは仏教が日本で発展してきた時に、それまでの日本の八百万(やおろず)の神々が仏に化身して権現となって現れているという神と仏が一緒になった神仏習合思想の考え方です。

このほか、境内には重源上人の像を安置している開山堂(鎌倉時代創建? 1520年再建)や、鐘楼堂(江戸時代初期建立)、経蔵、文殊堂、収蔵、不動堂、芭蕉の句碑「寿(すず)しさは飛騨の匠の 指図(さしず)哉」などがあります。
さらに昔はこの寺を守護するために周りを多くの寺が囲んでいました。現在浄土寺を管理しているのはそれらの寺で現存している「歓喜院(かんきいん)」と「宝持院(ほうじいん)」という寺が交代で務めています。
浄土寺の仏像の詳細
阿弥陀如来及び両脇侍立像【国宝】(1195年 仏師快慶作)〈像高 阿弥陀如来:5.3m、両脇侍右 観音菩:3.7m、左 勢至菩薩:3.7m〉

浄土寺の本尊である阿弥陀三尊像です。 三尊ともに仏師快慶の代表作で、浄土堂の中央の円形仏壇の雲座の上に立っています。
中尊の阿弥陀如来立像は、丈六(約4.85m)よりも大きな仏像ですので大仏の部類に入ります。
寺の縁起書には、「一丈六尺の金堂の阿弥陀如来と八尺の観音・勢至を各一体安置し、仏師快慶によって造られ、建久八年(1197)に落慶法要を行った」と記されているそうです。
仏師快慶は、重源とはかなり親しい関係にあったといわれており、重源上人の依頼によって、現地に来てこの仏像を彫ったと考えられます。
またこの仏像は中国の宋時代の仏画を手本にして造られたと解釈されていて、衣のヒダや両脇侍の髪形などにその特徴が現れているといわれています。

秘仏・薬師如来像(詳細不明)
薬師堂(本堂)に安置されている仏像です。浄土寺のもう一つの本尊です。しかしこの像は、歴代の住職も目にふれたことのない秘仏だそうです。

行基菩薩が創建したとされる「広渡寺」(浄土寺の西方約2km)が荒廃していて、そこの本尊の薬師如来像を浄土寺に移して、この薬師堂に祀ったといわれています。その後この薬師堂は火災にあっています。
.
阿弥陀如来立像【重文】(鎌倉時代1201年 仏師快慶)〈像高266.5cm〉

この仏像は現在「奈良国立博物館」へ寄託されています。
この阿弥陀如来像は「来迎会(らいごうえ:阿弥陀仏が死者を救済するために来迎する様を演ずる法会)」用の本尊として造られた像で、上半身は裸です。
そして実際に来迎会の儀式で使う時は、像に実物の薄い衣を着せ、像を台車に乗せて動かしたといわれています。
しかし、今はこの博物館に寄託されているので実際には来迎会の儀式には使われていません。
この阿弥陀像も浄土寺浄土堂に安置されている阿弥陀三尊像と同じ仏師快慶の作です。
重源上人坐像【重文】〈開山堂安置〉

浄土寺を建てた重源上人の像で、東大寺の俊乗堂に安置されている国宝の「俊乗房重源上人坐像(しゅんじょうぼうちょうげんしょうにんざぞう)」とほぼ同じ構図です。
まさに手に数珠を持ち、少し背を丸めた重源上人の姿は瓜二つといってもよいほど似ています。おそらく東大寺の像を模倣して造られたのでしょう。
浄土寺のこの像は、胎内に墨書銘があり、天福二年(1234)に奈良よりこの浄土寺へ迎えられ、建長八年(1256)に落成した御影堂に安置されたと書かれています。
以上、浄土寺の歴史や仏像のご紹介でした。
浄土寺阿弥陀堂では、阿弥陀如来像と二体の菩薩像が見られます。夏の夕暮れ時には沈みゆく夕日が後光を照らし、周囲の朱色と相成って仏像はさらに美しく輝きを増します。ぜひ自然と仏の融合の姿をぜひ体験くださいね。
浄土寺の御朱印

浄土寺の拝観料金、時間、宗派、電話など
正式名称 | 極楽山 浄土寺 |
宗派 | 高野山真言宗 |
住所 | 〒675-1317 兵庫県小野市浄谷町2094 |
電話 | 0794-65-4318(歓喜院)、0794-62-2651(宝持院) |
拝観時間・料金 | 9:00〜12:00 / 13:00~17:00 500円 |
周辺の観光地・口コミ |
.
.