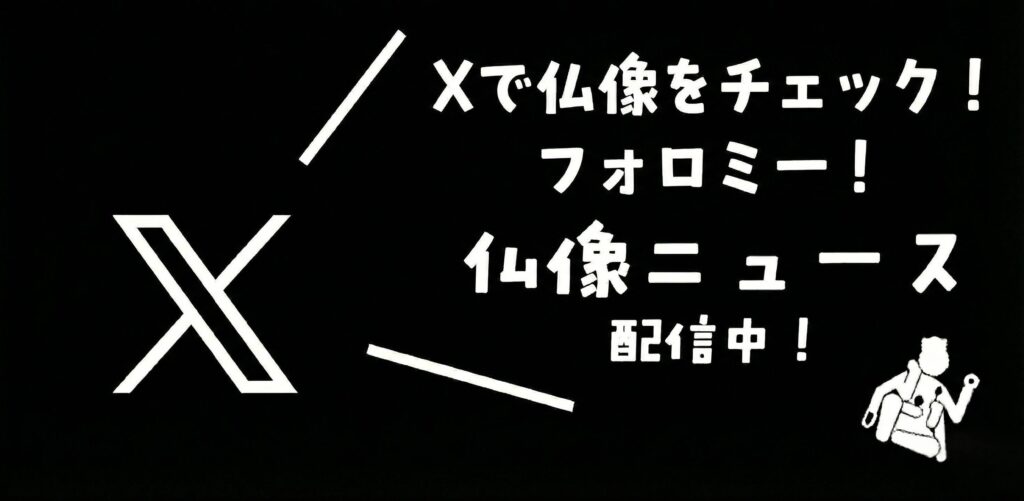【お盆にやるべきこと8選】お盆の時期はいつ?お墓参りや準備まとめ

夏になるとそろそろお盆です。お墓参りをする人は多いですよね。ご先祖様の魂があの世からこの世に帰って来るのがお盆の時期だからです。地域によって違いますが、だいたい8月の半ば頃のお盆にお墓参りに行く感じでしょうか。どうしてお盆という風習ができたのでしょうか?以下、ご紹介していきます。
お盆とは?お盆の由来

お盆は正式名称を「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言います。仏教の「盂蘭盆経」というお経に書かれた伝説が由来だとされています。「盂蘭盆会」はサンスクリット語の「ウランバナ」が語源で、ウラバンナ=逆さ吊りという意味です。

盂蘭盆会の伝説は次のようなものです。インド古代の仏教僧・木蓮(もくれん)は、ある日亡くなった母親が天国に生まれかわっているか確認するため、天眼で観察してみました。すると母親は天国どころか地獄の餓鬼界に落ちていて、逆さ吊りの刑にあっていました。驚いた木蓮が供物をささげると供物はたちまち炎を上げて燃え尽きてしまいます。困った木蓮はお釈迦様に相談。するとお釈迦様は「たくさんの僧が90日間の雨季の修行を終える7月15日にごちそうを用意してお経を読んで、心から供養しなさい」と木蓮に言いました。木蓮がその通りにすると、母親は地獄から浮かび上がって、喜びの舞を踊りながら天国へ昇って行きました。木蓮も踊り上がって喜びました。この木蓮の喜びの踊りが盆踊りの始まりと言われています。

仏教の創始者・お釈迦様の弟子の伝説がお盆の起源だったんですね。7月15日に、とお釈迦様がいったので、その時期がお盆になったようです。現在、日本のお盆は8月半ばだと認識されていますが、それはどうしてでしょうか?
お盆の時期はいつからいつまで?
お盆は、一般的には8月13日から16日の4日間とされています。昔の旧暦でいうと7月13日から16日がお盆で、これを現代の太陽暦にあわせると1か月後になります。1873年(明治6年)に日本では太陽暦を採用することになったので、分かりやすいようにちょうど一か月遅れにして8月15日前後をお盆としたんです。
お盆は地域によって時期がズレています。東京都市部、金沢市の旧市街地、静岡市などは7月13から15日がお盆で「東京盆」なんて呼ばれることもあります。そして「東京盆」と沖縄、鹿児島県奄美地方を除いた地域では8月13日から16日が「お盆」です。沖縄県と奄美地方では、今でも旧暦にそってお盆が行われます。そのため、年ごとにお盆の日付が違ってきます。
旧暦の7月15日が、太陽暦にかわって1か月遅れたんですね。7月に行われるお盆を新盆(にいぼん)、旧暦の7月にあたる8月に行われるお盆を旧盆(月遅れ盆、8月盆)とも呼びます。
さて、お盆の時期が分かりましたね。では次はお盆の前にやる準備についてみてみましょう。
お盆の事前準備
まずは、お盆を迎えるための準備があります。大切なのは1日と7日です。
お盆が行われる月の1日
お盆が行われる月の1日を「釜蓋朔日(かまぶたついたち)」といって、地獄の釜のふたが開く日とされています。ちょっとおどろおどろしいですね。この日を境にお盆の準備がスタートします。だいたい
・お墓の掃除と事前のお墓参り
・仏壇の掃除
・盆提灯、灯篭(とうろう)の用意
という準備が行われます。

お盆が行われる月の7日
次の準備段階は7日です。この日を「棚幡(たなばた)」と呼びます。旧暦ですと、7月7日で「七夕」のことですね。7日の「棚幡」では、ご先祖様をお迎えするための「精霊棚(しょうりょうだな)」をセットします。

精霊棚は、いろいろなやり方はありますが一般的には仏壇の前に敷物をしいて経机か小机を置いてセットします。机には位牌を置きます。東日本ではナスやきゅうりに割りばしや串などを指した四本足の精霊馬(しょうりょうま)を用意し精霊棚に並べます。

ナスは牛、きゅうりは馬を表します。精霊馬はご先祖様があの世からこの世へ行き来するための乗り物なんです。この世へ来るときはきゅうり馬で早く来て、あの世へ帰るときはナス牛でゆっくり帰ってね、という願いが込められています。精霊馬、西日本では作る風習がありません。西日本ではかわりに精霊舟や精霊流しをする地域もあります。

さて準備がすんだらお盆に入ります。次はお盆でやることについてまとめます。
お盆にやること

地域によってお盆に何をするのかは違ってきます。また、亡くなった人を初めて迎える初盆(はつぼん:死後四十九日が過ぎてから初めて迎えるお盆)は普通のお盆よりももっと丁寧に供養を行います。初盆は新盆とも呼ばれます。親族や亡くなった人と親しかった友人を招いてお盆法要を盛大に行うこともあります。今回は、お盆でやる一般的なものをご紹介します。
お墓参り

お盆でやることといえば、まず思い浮かぶのはお墓参りでしょう。お墓参りはだいたい13日に行くのが一般的です。多くの地域では、8月13日が迎え盆と呼ばれる、ご先祖様をお迎えに行く日にあたります。
お墓参りの手順は、だいたい次のような感じです。
お墓の前で合掌
お墓の掃除
墓石に打ち水をして清める
お供えをする
お線香をあげて再び合掌
後片付け
迎え火と送り火
お盆の初日には、ご先祖さまの魂を迎えるために「迎え火」を焚きます。この時使われるのが盆提灯です。お盆の時期、玄関先などに吊るしてそこに火をともす提灯を盆提灯と言います。盆提灯は亡くなった人がこの世に戻って来るとき、迷子にならないよう、目印として飾ります。初盆/新盆の場合は、白提灯を玄関や軒先に飾ります。

迎え火は家の玄関やお墓で行われます。焙烙(ほうろく)という素焼きの平たいお皿の上にオガラを置いて火をともします。家ではなく、お墓で迎え火をするケースもあります。その場合は、オガラの火を盆提灯に移して家へ持って帰ります。そして家に用意してある別の盆提灯に火を移して、お墓から持ってきた盆提灯は黙祷をしてから消します。盆提灯の聖火リレーみたいなものですね。
盆提灯はだれが用意してもかまいませんが、白提灯は家族が用意します。そして初盆が終わったら白提灯はすぐに送り火で燃やすか菩提寺にお焚き上げしてもらってすぐに処分します。
お盆が終わる時は「送り火」をします。家で火を灯して、盆提灯でお墓や玄関先などまで亡くなった人を案内します。送る場所まで着いたら、火を消して黙祷をします。
お供え
お盆はご先祖様が帰って来るので、おもてなしのために精霊棚にお供え物をします。お供え物は、「五供(ごく)」といってお香、お花、ろうそく、お水、食べものの五つにするというルールがあります。このルールにのっとって、お線香、お花、ろうそく、お菓子などをお供えします。亡くなった人が好きだった食べものでもOKです。

お盆法要などで参列者から食べもののお供え物を頂いた場合、「すぐに食べられる状態」にしてお供えします。包装されたお菓子は小袋にして、果物ならば皮をむいてお供えするのがマナーです。精霊棚の横には、提灯をおきます。お盆の間は提灯の灯りをつけておきます。
盆踊り

お盆と言えば「盆踊り」を真っ先に思い浮かべる人もいるでしょう。盆踊りのはじまりは平安時代です。空也というお坊さんがはじめた踊念仏がお盆の行事と結びついたのが盆踊りと言われています。
地域によってさまざまな盆踊りがあって、踊りの振り付けや曲もさまざまです。ソーラン節、八木節という民謡系のものから、現在はJ-POP系、ディスコ系の曲もあります。盆踊りでは、手ぬぐいを顔にまく頬かむりをすることがありますが、これは亡くなった人に扮して踊り、死者を弔うという意味があります。また盆踊りで組まれるやぐらの上には盆棚を飾る地域もあります。
その他のお盆行事
地域によって違っているお盆の風習。時代がたつにつれ、地域ごとの特色を持つお盆行事がいろいろと行われるようになりました。その中でも有名なのは京都の「大文字焼き」と北九州地域で行われる「精霊流し」「灯篭流し」でしょうか。長崎県の「精霊舟」による精霊流しはよくニュースにもなりますよね。どれも送り火の風習が大規模になったものです。また打ち上げ花火もご先祖様をお送りする精霊送りの概念から始まりました。

またお盆の時期にはお中元を贈りますよね。江戸時代になると「盆礼」といってお盆の時期に親戚や知人の家を訪ねて贈り物をするようになりました。これがお中元につながっているそうです。
お盆についていろいろとご紹介しました。それではまとめに入りましょう。
まとめ
お盆についてまとめると次のようになります。
お盆は正式名称「盂蘭盆会」といって、サンスクリット語の逆さづりを意味する「ウラバンナ」が語源
お釈迦様の弟子だった木蓮が地獄におちた母親を助けたエピソードからお盆の風習が生まれた
お盆はかつて旧暦の7月13日から16日に行われていたが、明治時代に太陽暦を採用するにあたって8月に1か月ズレた。そのまま7月がお盆の地域もある。7月を新盆、旧暦を1月ズラした8月を旧盆という。
お盆では精霊棚、お供え物、盆提灯でご先祖さまをお迎えする。お墓参り、迎え火、送り火をするのが一般的。送り火の風習が大規模になった行事が「大文字焼き」「灯篭流し」。
盆踊りは平安時代の踊念仏がお盆と結びついたもの。打ち上げ花火は精霊送りから、お中元は江戸時代の「盆礼」から始まった。
梅雨があけたら夏。夏になるとお盆ですね。遠くにお墓参りに行く人もいるでしょうか。普段はなかなか仏壇に手を合わせたりお墓参りをする機会がない人もいるでしょう。盆踊り、打ち上げ花火を楽しみつつ、ご先祖様をお迎えして供養できるお盆。お盆には人それぞれに夏の思い出がたくさんありそうですね。