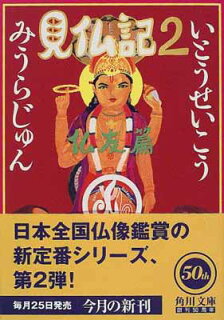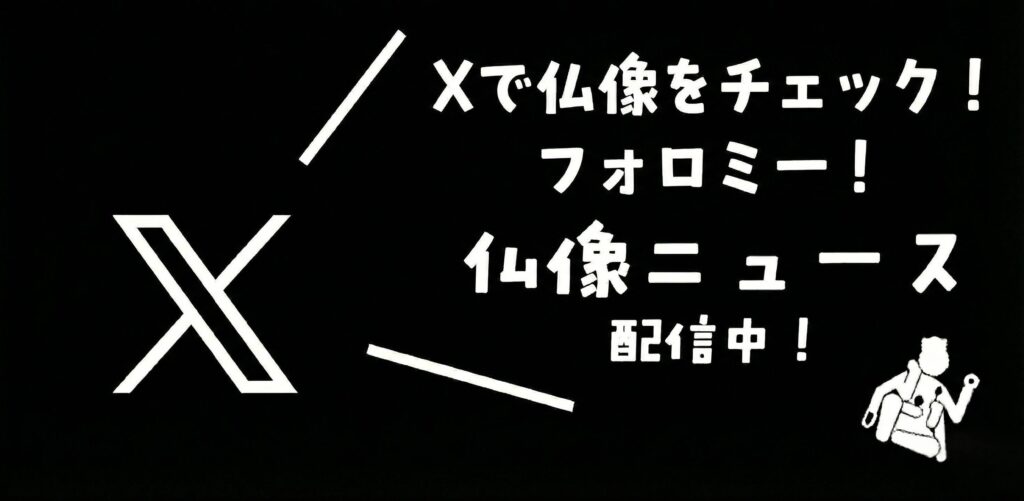【みんなの好きな仏像1位は?】第1回仏像トーナメント結果発表!

先週末、仏像リンクの Twitter では、”仏像トーナメント“というイベントを開催し、皆様から一番好きな仏像についてのツイートを募集しました。
この企画に対して、147のリツイート、84の引用ツイート、そして108返信(2023年6月12日時点)という、大変な反響をいただくことができました。皆さまからたくさんのご協力をいただき、誠にありがとうございます!
今回は、そのツイートの中から得票数の多かった仏像や、仏像リンクの独断と偏見による各賞を発表させていただきたいと思います。
順位についてはこの仏像トーナメントにちなんで、1位:如来、2位:菩薩、3位:明王、4位:天として順位付けを行いました。しかし、この順位はあくまで今回の企画の一環であり、仏像の本来の価値を測るものではありません!

では、行ってみましょう~!!
天部賞(第4位) 寿宝寺(京都)|千手千眼観世音菩薩像
昼と夜のお顔の違いにドキッとさせられる♡
寿宝寺
十一面千手千眼観世音菩薩 https://t.co/tHh3HQu9qH pic.twitter.com/zfm16NDAym— みゆみゆ (@miyumiyubutsu) June 10, 2023
第4位は京都寿宝寺がランクイン!ここのお寺には本当に千本の手を持つ珍しい十一面千手千眼観音立像があります。普段は見えない手のひら一つ一つに目が書かれていて、それが「千手千眼観音」と呼ばれる理由です。
この観音像は、普通は42本の手を持つことで「千手」と言われるけれど、ここでは本当に千本の手があります(これを真数千手観音と言います)。この像以外にも本当に千本の手を表す千手観世音で有名な像として大阪の藤井寺や奈良の唐招提寺の像などがあります。
そして寿宝寺の観音像は、特別な演出があるんです!それはお寺の方が収蔵庫の扉を閉めていただき千手観音さんの闇の顔、そして扉を開けて光の顔と、その両面を楽しませていただける演出があります!

明王賞(第3位) 渡岸寺観音堂(滋賀)|十一面観音像
先日初めてお会いした
滋賀県長浜市高月町渡岸寺観音堂(向源寺)
国宝 十一面観音立像ただただ綺麗でした✨ https://t.co/wYONKvefny pic.twitter.com/p7wkqqk5MS
— sumimo (@sumimo69) June 10, 2023
第3位に選ばれたのは、滋賀県湖北に位置する渡岸寺観音堂の十一面観音像です。絶世の美女とも言えるほどの美しさを持つこの菩薩像は、女性的な魅力が強く感じられます。その美しさは、一見するだけで感動を覚えるほどです。もちろん、この十一面観音像は国宝に指定されており、国宝の十一面観音は日本全国にいくつかありますが、ここにある観音像は多くの人を虜にして全国からたくさんの人が見にやって来ます。
十一面観音像の高さは、人と同じくらいの194cmです。立っている姿や、ふっくらしたお顔、すこし腰をひねった姿などから感じられます。お顔はとても穏やかで、目を閉じていて、うっとりと優しく見えます。さらにここの拝観環境は十一面観音像を後ろからも360度全体から拝観することができるんです。なんて贅沢!特に、頭の上には十一の顔があり、その中には笑っている顔もあるんです。この笑顔は、悪いものを追い払うためだとも言われています。ぜひ後ろから拝観して見つけてみてください。


天部賞(第2位) 高野山霊宝館(和歌山)|深沙大将立像
金剛峯寺の木造深沙大将立像。首飾りに目が釘づけになった。鎌倉の仏師の工房には本物の頭蓋骨があって模したに違いない、という確信を得た作だった。快慶の作だとわかったのはあとからのこと。展示室でしか観ていないので、お堂に据えられた状態で観たい。 https://t.co/UhjusHLQLV pic.twitter.com/nTcyMhb9QK
— 旅月庵 (@ryogetsuan) June 11, 2023
第2位は高野山霊宝館の深沙大将立像です!『西遊記』という物語は、多くの人が知る中国の有名な物語ですがその中に登場するのが、この深沙大将という守護神です。彼は主人公の三蔵法師(玄奘)がインドへ旅をする際に、彼を守ってくれた恐ろしい鬼の姿の仏さまなんです。ちょっとこの恐ろしい顔からはイメージしにくいかもしれませんね。例えるなら、まるでボディガードのような存在です。旅人を守ることが彼の役割であり、その力は「般若経」という仏教の教えを守る仏とも言われています。
深沙大将の姿を表すとき、象の口から足が出ている絵が描かれます。これは彼の巨大さを示すためです。考えてみてください、象から足が出ているなんて、なんて大きいんでしょう!
また、彼のズボンは「象皮の面」と呼ばれ、象の皮を象った半ズボンのような形です。インドでは象は知恵と力の象徴とされ、神聖視されています。そして、深沙大将の胸には7つのドクロが飾られています。これは主人公である三蔵法師が生まれ変わった7つの生涯を象徴しているとされています。また、お腹の部分には人の顔が描かれており、これは深沙大将が童子に取り憑いていることを示しています。
日本では、京都の金剛院などに深沙大将の仏像があります。でも高野山霊宝館の深沙大将像は見る者に強烈な印象を与える仏像としてはピカ一です。

如来賞(第1位) 安倍文殊院(奈良)|文殊菩薩騎獅像
ん〜№1は全てにおいて完璧な安倍文殊院の文殊菩薩騎獅像ですかね! https://t.co/6Z4A4PTVMO pic.twitter.com/M0mz7dWMjB
— ぶちゅぞう (@9vbkXWhFWqqhkSz) June 10, 2023
そしてそして!第1位は安倍文殊院の文殊菩薩騎獅像となりました。
鎌倉時代を代表する仏師、快慶が手掛けた仏像で、「知恵の仏様」を象徴するとっても美しい仏像です。総高約7メートルというとっても大きな文殊菩薩の像が、獅子の上に座っている形と、その周りに4体の小さな仏像がいる構成となっています。これら4体の仏像は、特定の仏教の仏様や聖人を表していますが、一般的な名前とは異なり、この場所では独自の名前で呼ばれています。
文殊菩薩の像の中には、「アン阿弥陀仏」(これが快慶の署名)と彼の助手たちの名前が記されています。
この像は、東大寺(大きな仏教寺院)の復興のための大イベントに合わせて作られ、その制作は大急ぎで行われました。 ただし、一部の小さな像(最勝老人、つまり「維摩居士」と呼ばれる像)は、文殊菩薩の像よりも後の時代(1607年頃)に作られたもので、文殊菩薩が座っている獅子も後から追加されました。この仏像群は、2013年に日本の重要な文化財として「国宝」に指定されました。


特別賞
粉河寺(和歌山)|千手観世音菩薩
滑り込み恐縮です。数多くありますが粉河寺千手観音立像を推させていただきます。秘仏御本尊に成り代わり本堂裏で参拝者を受け入れるお姿が数年前の調査以前から大好きでした。元々は十一面観音として造像されていたことや小手に玉眼が施されていることも分かったようで、魅力溢れる仏様だと思います。 https://t.co/2etYTITPZA pic.twitter.com/qWwPl73Q0M
— すゐしん (@1994_Suishin) June 11, 2023
西国三十三所第三番札所の粉河寺の本尊は絶対秘仏の千手観音です。千手観音は、十一面の顔と千本の手を持ち、その手のひらに千の眼があるとされ、苦しむ人々の救済者とされています。
一般の人々が拝むことができるのは、本堂背面に立つ千手観音像です。この像は、江戸時代の火災後に、平安時代後期の観音像から改変されたものだとされています。

金剛寺(大阪)|降三世明王坐像
天野山金剛寺の木造降三世明王坐像
なら仏像館で公開されていたときに見て
その迫力に圧倒されました— naka (@farcona) June 10, 2023
金剛寺は大阪府河内長野市に位置する真言宗御室派の古刹で、本堂には寺宝である降三世明王坐像が存在します。大日如来坐像の脇侍として不動明王坐像とともに金堂に安置されています。 この降三世明王坐像は、行快という仏師が1234年に作った作品で、その高さは201.0cmにも及びます。像の身体は青黒く、火焔光背は赤色、その内側は緑色、装飾品は金色、歯は白色と、鮮やかな色使いが目を引く美術作品です。
最近の修復作業によってこの像が快慶の弟子・行快により作られたことが明らかになり、更には新たに国宝に指定されました。2メートル以上の大きさと色彩豊かなデザインが、その忿怒の表情と合わさることで観る者に強烈な印象を与えます。
降三世明王坐像のグッズが欲しかった
奈良国立博物館では写真集に載ってたけど、金剛寺ではポストカードと切手に小さく映ってるだけで
私「推しのグッズ欲しかった~」
娘「推しとかグッズとか言うな罰当たりww」 pic.twitter.com/bcOvKh0bTh— IO(イオ) (@hydeist0605) September 20, 2020

深大寺(東京)|釈迦如来倚像
#仏像トーナメント
「一番好きな…」。。なんという酷な事をおっしゃるのでしょうね
※多くの仏像が集まるように…フムフム、では#深大寺 白鳳仏を推しておきます。(自分に嫁入り先、本籍地近所でして)
この微笑みに癒されない人はいないでしょもちろん美味しい #深大寺蕎麦 も一緒に! https://t.co/8lHfq8wBt2 pic.twitter.com/Q8WVi2xCng
— 鴨つけ汁蕎麦 (@kamostuke) June 10, 2023
深大寺に伝わる7世紀から8世紀に制作された高さ約84cmのお釈迦さまの像です。つまり、これは1200年以上前のもので、深大寺の長い時間の流れの中では一度忘れ去られてしまっていたんですね。しかし、1909年に柴田常恵という学者によって再発見され、その後、全国的にその存在が知られるようになりました。
釈迦如来像はその細部までこだわった造形が注目されています。たとえば、両手は前に出され、ちょっとだけ曲げられています。衣服も一部が左肩からかけられ、右肩に少しあてられています。これらの細部の表現が、仏像の美しさを引き立てています。 特に、この仏像は「倚像」と呼ばれる特殊な形式で作られています。これは、仏像が腰掛けて座っている形を指し、日本の歴史で飛鳥時代から奈良時代にかけて(大体1300年前から1200年前くらい)によく見られました。
仏像自体は、全体が空洞になっていて、全体の厚さは約1cm、重さは53kgです。外見は金色に輝いていますが、この金色の仕上げはどのように施されたか、今もなお調査中です。 そして、この仏像は最近、「国宝」となりました。同じ国宝に指定された他の仏像と比べても、この仏像は東日本で最も古いものであり、東京都内の寺院から発見された仏像としては唯一のものです。こんなとっても古い仏像がなぜ東日本の深大寺から発見されたのか、とても美しく楽しい東京ミステリーの一つと言っていいかもしれません!
総括
いかがでしたでしょうか。Twitter上で行った、仏像リンク主催の「第1回仏像トーナメント」結果が出揃いました!愛する仏像を選ぶ、非常に悩ましいトーナメントでしたがおかげさまで、数多くのフォロワーさんから熱烈な投票が寄せられました。
表彰台に輝いたのは以下のスーパースターたちです!
- 【如来賞(第1位)】 文殊菩薩騎獅像(奈良・安倍文殊院)
- 【天部賞(第2位)】 深沙大将立像(和歌山・高野山霊宝館)
- 【明王賞(第3位)】 十一面観音像(滋賀・渡岸寺観音堂)
- 【天部賞(第4位)】 千手千眼観世音菩薩像(京都・寿宝寺)
そして、特別賞として選ばれたのは、以下の3つの仏像。
- 粉河寺(和歌山)の千手観世音菩薩
- 金剛寺(大阪)の降三世明王坐像
- 深大寺(東京)の釈迦如来倚像
すべての仏像にはそれぞれの魅力があり、今回選ばれた仏像たちにも私たちの心を掴む何かがあります。それぞれの仏像がどんな物語を語ってくれるのか、ぜひ、ご自身の足で訪れてみてください!
次回の「仏像トーナメント」もお楽しみに!日本全国にはまだまだ素敵な仏像がたくさん。次はあなたが見つける番!自分だけの1体に出会う旅を楽しんでみてくださいね。
【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう
新TV見仏記
地方仏を歩く|丸山尚一
【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア
図説 みちのく古仏紀行
■関東エリア
東京近郊仏像めぐり
■東海エリア
東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重
■関西エリア