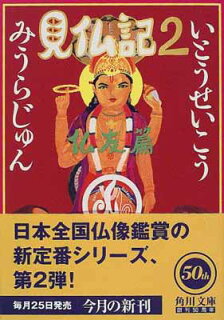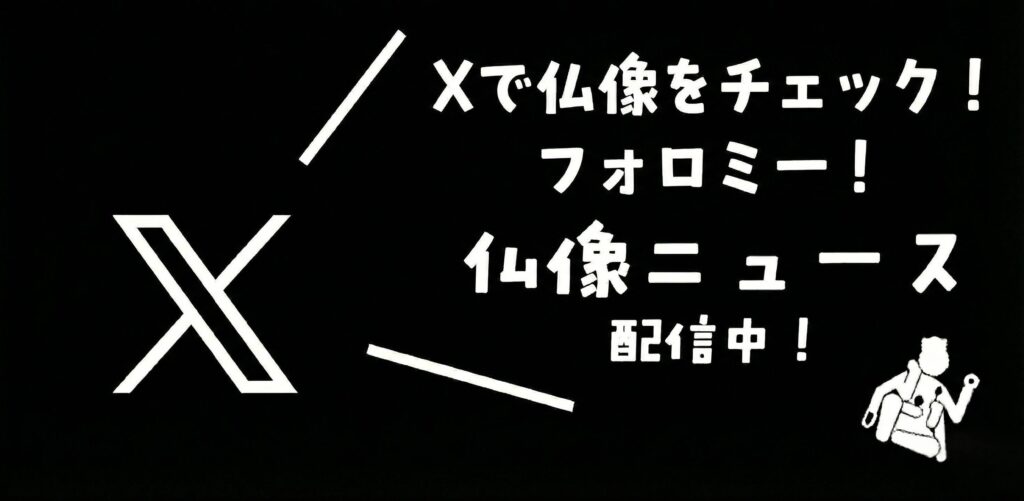山梨県福光園寺の仏像-吉祥天及び二天像・香王観音立像を訪ねて

“山梨の仏像めぐり”といえば甲州の大善寺・薬師如来日光月光菩薩(秘仏)・十二神将像、甲府市にある甲斐善光寺の阿弥陀如来、甲州市にある放光寺の大日如来、天弓の愛染明王あたりが思い浮かぶけど、それらの仏像と“山梨の仏像めぐり”で双璧を成す仏像を有するのが、今回ご紹介する福光園寺(ふっこうおんじ)です。
福光園寺は甲府盆地の美しい風景を望むことのできる歴史的な寺院。その中には、鎌倉時代の名匠・蓮慶が製作した仏像たちが安置されています。穏やかな姿態、精緻な造形技法、そして独特の表情。山梨の仏像を語るには欠かすことができない蓮慶という存在。その深い魅力に迫ることで、山梨という地の仏像の技術の高さを改めて感じることができるかもしれません。


この記事はソゾタケさん等、仏像リンクのメンバーから提供いただいた写真をご紹介しております。
福光園寺の場所・アクセス方法
 御坂山地が織りなす緑の海の中に、静寂と歴史が息づく福光園寺がたたずみます。東西に連なる山梨県南部の山々は、甲府盆地と富士山・富士五湖を隔ててできるこの地は、新生代新第三紀の堆積岩と花崗岩で形成されています。
御坂山地が織りなす緑の海の中に、静寂と歴史が息づく福光園寺がたたずみます。東西に連なる山梨県南部の山々は、甲府盆地と富士山・富士五湖を隔ててできるこの地は、新生代新第三紀の堆積岩と花崗岩で形成されています。
笛吹市御坂町大野寺の甲府盆地南東端、果樹園が広がる傾斜地に佇むのが福光園寺です。寺に伝わる「甲斐の黒駒」の伝承は、聖徳太子が富士山頂に達したという伝説と深く結びついています。
おもなアクセス方法
– 石和温泉駅からバスで30分、徒歩で10分
– 車で行く場合は、中央自動車道笛吹ICから約20分
福光園寺の拝観方法・拝観環境
福光園寺の拝観方法
福光園寺はお寺に事前予約することで拝観ができます。
拝観時間は9時から17時までです
拝観環境

境内には古刹の雰囲気が漂っています。境内には樹齢900年といわれる杉の木や、春には樹齢200年の枝垂桜などがあり、美しい景観が広がっています。私たちが訪問したときは夏真っ盛り。青々とした美しい空と緑が広がっていました。
福光園寺の歴史・由来

福光園寺は、真言宗智山派の歴史ある寺院です。元々は「大野寺」として知られ、戦国時代に現在の「福光園寺」という名に変わりました。この名前の由来は、『金光明最勝王経』に照らし合わせると、「吉祥天は妙華福光の園の城に住む」との記述から来ているとされます。
福光園寺の歴史は、推古天皇の時代に聖徳太子によって創建されたとの伝承があります。行基菩薩や弘法大師などの著名な僧侶たちもこの寺と深い繋がりを持っていたと伝えられています。真筆の般若心経や、多くの重要な文化財がこの地に残されているものの、火災を始めとする災害によって、その詳しい歴史の一部は失われてしまいました。
福光園寺の境内は、自然に恵まれています。特に、樹齢900年とされる杉や、春に花を咲かせる樹齢200年の枝垂桜やソメイヨシノが、その美しさを増しています。
福光園寺は、歴史と自然、そして貴重な仏像によって、訪れる者たちに深い感動を提供してくれる場所となっています。
福光園寺の仏像について

福光園寺の本堂のとなりには大変大きな収蔵庫が建てられており、その中に鎮座しているのがこれからご紹介させていただく3体の仏像です。
吉祥天坐像|重要文化財(国指定)

福光園寺のメインはやはり鎌倉時代前期の1231年に制作された吉祥天坐像でしょう。この仏像の制作者は、有名仏師運慶の弟子である仏師“蓮慶”で、彼は山梨県内の大善寺の十二神将像も手掛けた人物として知られています。吉祥天像の美しい横顔や、華やかな衣の模様、清々しい顔立ちは、多くの参拝者を魅了しています。
この坐像の高さは約110センチと堂々たるもの。ヒノキの寄木造という技法で制作され、玉眼の瞳が清々しさを放っています。この玉眼は後補で変わっているものの、それがさらに独特の魅力を与えています。
吉祥天の鑑賞のポイント3点
①力強さと男性的な要素:
吉祥天は本来、女神であり、女性らしい姿が一般的。しかし、この吉祥天像は「堂々たる、力強い男性的な」姿をしており、その点で他の鎌倉時代の吉祥天像とは異なる。この独自の解釈は、仏師蓮慶の作風の独特さが反映されている可能性がある。「母ちゃん、やったるで!」という頼りがいのある女性に思えます笑
②坐像の特異性:
通常、吉祥天像は立像として制作されることが多いが、福光園寺の吉祥天像は坐像である。坐像での吉祥天は図像中に見られるものの、彫像としては非常に珍しい。この坐像の形式が、観る者に「圧力感」や「威厳、威力」のような発散パワーを感じさせる要因となっているかもしれない。
③中尊・主尊としての配置:
この吉祥天像は、脇侍に二天像(多聞天(夫)、持国天)を伴う中尊・主尊として造立されている。これは、吉祥天像の重要性や特異性を強調するものと考えられる。
■一般的な吉祥天像


二天像(持国天・多聞天)|重要文化財(国指定)

吉祥天像の隣に持国天像と多聞天像、通称「二天像」も祀られています。これらの立像は、それぞれ像高が120センチ程度で、怒りの表情を浮かべながらも、どこか優しい眼差しを持っています。制作技法や材料は吉祥天像と同じく、ヒノキの寄木造と玉眼嵌入が用いられています。顔の迫力は“さすが慶派!”といった具合。でも全体のポージング等、動き自体はとっても静かに感じました。迫力はやや控えめながらも、その調和の取れた姿や、破綻のない立ち姿は、仏師蓮慶の技量の高さを感じさせます。
香王観音立像|重要文化財(県指定)

福光園寺には、重要な仏像「香王観音立像」があります。この仏像は、奈良時代の著名な僧・行基が創作したとの伝説が残っています。すごいですよね行基伝説。また、昭和34年に山梨県指定文化財に認定された、文化的価値の高い仏像です。

香王観音立像はケヤキ材を使用しており、一木造の技法で造られています。像の高さは152cmあり、その姿は重厚感を漂わせています。かつては彩色や漆箔で装飾されていたと言われますが、現在は身体中の彩色は残っておらず跡を見ることはできません。宝冠や両手、足先は失われていますが、台座や光背は後代に補完されています。
福光園寺の敷地内の観音堂には、この香王観音立像とともに不動明王像が収められていたそうです。しかし、惜しいことに不動明王像は火災で失われました。伝説によれば、火災の際に香王観音立像は井戸の中に隠され、火の難を逃れたと言われています。
香王観音だけでも残ってくれてよかった。
三十三観音としての香王観音:
観音様は、世を救済するために様々な姿で現れると言われており、その中の一つが香王観音です。この香王観音は、瑠璃観音とも呼ばれ、自在天身を表しています。香炉を持ち蓮華に乗る姿は、水難や厄除けの観音様として知られています。ただよくよく見ると“観音”とされていますが来ている衣服は天部の造形にも思えてきます。
仏師・蓮慶(れんけい)とは
この福光園寺の吉祥天像・二天像を製作したとされる蓮慶(れんけい)についてご紹介させていただきます。蓮慶は鎌倉時代の代表的な仏師として知られ、慶派という流派の一員としてその名を馳せています。彼が手がけた仏像は、山梨県の福光園寺や大善寺などに現存し、多くの貴重な文化財として評価されています。
蓮慶の代表作:大善寺の十二神将像
山梨県甲州市にある大善寺にも、蓮慶の作とされる十二神将像があります。この神将像は、各像が四尺を超える大きさであり、甲制や体勢もさまざまな変化に富んでいるのが特徴です。制作年や詳細な背景についての確固たる記録は乏しいものの、像内の墨書から蓮慶の名前や制作時期が確認されています。
蓮慶と運慶の混同
歴史的に「蓮慶」という名前は、「運慶」と混同されることがあったようです。実際に、福光園寺や大善寺の記録では、「運慶」が作者として記されていたこともあったようですが、近年の研究や像内墨書の発見によって、正確に「蓮慶作」とされることが明らかとなりました。
蓮慶の活動地域について
蓮慶の作品が山梨の二つの寺に残されていることから、彼が関東地方での活動が中心であったかのように考えられがちです。しかし、実際には都や中央で活動していた仏師であったとされています。
まとめ

福光園寺の敷地を歩いていると、その歴史と美しさに圧倒されました。吉祥天像の隣に佇む「二天像」、持国天像と多聞天像の存在感には本当に心を奪われました。その力強さの中にも優しさを秘めているように感じました。
福光園寺の拝観料金、時間、宗派、電話など
正式名称 | 大野山 福光園寺 |
宗派 | 真言宗智山派 |
住所 | 山梨県笛吹市御坂町大野寺2027 |
電話 | 055-263-4395 |
拝観時間 | 事前予約制 9時00分~17時00分 |
拝観料金 | 志納 |
.
.

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

地域タグ:山梨県
★周辺のおすすめ寺院★
【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう
新TV見仏記
地方仏を歩く|丸山尚一
【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア
図説 みちのく古仏紀行
■関東エリア
東京近郊仏像めぐり
■東海エリア
東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重
■関西エリア
1冊でわかる滋賀の仏像 文化財鑑賞ハンドブック
奈良仏像めぐり(たびカル)
京都仏像めぐり (たびカル)