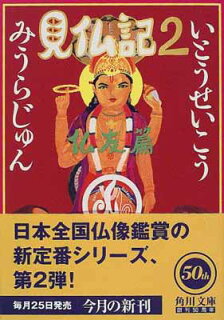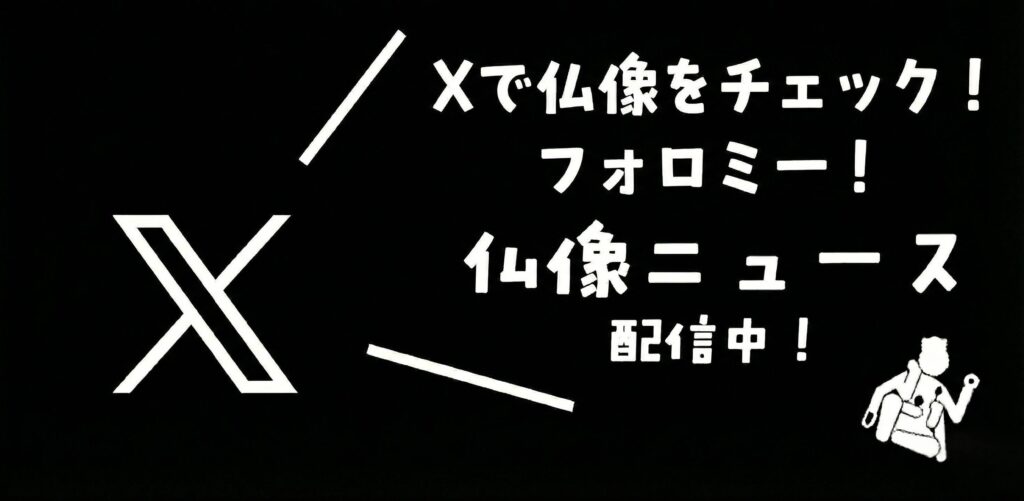福井県二上観音堂への仏像の旅-秘仏十一面観音立像を訪ねて

福井県福井市にある二上観音堂で、33年に一度の特別な御開帳が行われました。かねてよりずっとお会いしたかった重要文化財に指定されている十一面観音菩薩像が拝観できるチャンスということで、GWの予定をここにさだめて北陸道をひた走りました。
この御開帳での出会いは、仏像リンクのメンバーたちとの再会でもあり境内には多くの知り合いがおり、十一面観音さんを前に同窓会のような雰囲気に包まれていました。
この貴重な体験をぜひ、多くの方に知ってもらいたいと思います。
二上観音堂の拝観日時・拝観環境
2023年5月4日、5日の朝10時から夕方5時まで拝観ができるとのことでしたが、午前中は法要があり午後からがおすすめとのことで午後13時ころを目指していきました。
駐車場は観音堂の近くにありかなり広くとられていましたが、混み合っておりましたがしっかり誘導係の方が大勢いらしたので混乱することはありませんでした。
※さらに混雑の場合は近くの文殊公民館などに誘導されることがあったようです。
二上観音堂の歴史と由来
 二上観音堂の歴史について、詳細な情報は限られていますが、各年代別にはこのような歴史がある可能性があります。
二上観音堂の歴史について、詳細な情報は限られていますが、各年代別にはこのような歴史がある可能性があります。
奈良時代(8世紀):
二上観音堂の地域には、奈良時代に東大寺の荘園(糞置荘)が置かれていたとされています。そのため、観音堂自体の歴史も奈良時代に遡る可能性があります。また、十一面観音菩薩立像の制作時期も8世紀半ばとする説が存在します。

平安時代(9世紀 – 12世紀):
平安時代の詳細な記録は乏しいものの、文化遺産データベースでは、二上観音堂の十一面観音菩薩立像が10世紀初めの作とされています。
江戸時代(17世紀 – 19世紀)以降:
江戸時代以降の二上観音堂に関する情報は明確ではありませんが、この時代には既に観音堂が存在していたことが考えられます。
現代(20世紀 – 21世紀):
近年では、33年に一度の御開帳が行われ、多くの参拝者が全国から訪れるようになりました。また、立像が秘仏とされており、普段は公開されていませんが、特別な機会に公開されることがあります。

二上観音堂に祀られる仏像

二上観音堂には、33年ぶりに公開された十一面観音菩薩立像があります。この立像は非常に貴重で、福井市立郷土歴史博物館に寄託されているにも関わらず、秘仏として公開されていませんでした。今回十一面観立像は、普段保管されている福井市立郷土歴史博物館から33年に一度のご開帳で2日間だけ元の場所に戻され特別に公開されることになりました。

十一面観音菩薩立像

製作時代: 8世紀半ばとされる説がありますが、文化庁の文化遺産データベースでは10世紀初めの作と説明されています。
像高: 187cmほど
材質: 檜の一木造り、内刳りなし
その他の特徴: 連眉(れんび:左右の眉がつながる)、大きな耳、若々しい胸の筋肉、左肩から右脇腹に垂れる衣の柔らかさなどが特徴です。
十一面観音は顔の半分まで御簾がかかっていたため、少し屈んだ状態で拝観することで全身の姿を確認することができました。特に目を奪われたのは、お腹のあたりから足にかけての衣紋の表現。うずまき状の衣紋やカーテンのドレープのような衣紋表現が見事で、その姿に見とれてしまっていました。どっしりとした安定感があり、この山の信仰とともに存在してきた仏像である説得力を感じました。

連眉の仏像
連眉(れんび)の仏像は、左右の眉が真ん中でつながっている特徴があります。この表現はインドや中央アジアの民族に見られ、日本では珍しい仏像の表現方法になります。有名な連眉の仏像には、奈良国立博物館に展示されている如意輪観音像や勝尾寺の薬師三尊像中尊などがあります。

連眉の表現はエキゾチックで凛とした印象を与えますが、インド風のエキゾチックさだけでなく、厳しく恐ろしい威相を表現する像もあります。日本の連眉表現の仏像は、作例が少なくバラエティーに富んでいます。その意図や系譜は一律には定まらず、価値の転化が見られます。
木造多聞天立像 木造広目天立像

本尊十一面観音立像の脇侍として祀られている二天像、木造多聞天立像と木造広目天立像があります。多聞天像は宝塔と戟を持ち、閉口して立ち、広目天像は開口し、戟と索を持って立っています。
これらの像は一材の針葉樹から彫られており、内刳りは施されていません。また、躍動感は少なく、落ち着いた表現が特徴です。平安後期の仏像の和様化が見られ、制作は十一世紀頃と推察されます。
二上町の言い伝えでは、かつて四天王の他の二尊も存在したとされますが、現在は別の地域に移されていると言われています。しかし、阿吽動と静を表す二軀の存在から、当初は二尊一対で造像された可能性もあります。
二上観音堂の次回の御開帳はいつ?
二上観音堂のご開帳サイクルは33年に1度です。新聞の記事によると、次回のご開帳は2055年とのことではありますが、実際には17年に1度の半開帳の可能性もありますし、何と言ってもこちらの仏像は福井県立歴史博物館さんが保存されていらっしゃるので、もしかしたら何らかの企画展などのタイミングでお披露目となる可能性もなきにしもあらずかなと予想します。
二上観音堂周辺のグルメ

福井に訪問して毎回食べるものと言ったらソースカツ丼。家でとんかつをご飯の上に乗せるというのとは、また一味違う。福井のソースカツ丼ならではの絶妙なジューシーさとソースのコクを感じることができるので、私は福井に行ったら毎回ソースカツ丼を食べてる気がします。
今回訪問したのは福井市にある「とんかつ味処くら」です。ソースカツ丼の名店といえばヨーロッパ軒さんが有名ではありますが、今回行列に並ぶ時間がなかったので、比較的大きな店舗であるこちらのお店を訪ねました。
一口にソースカツ丼と言ってもこちらの店ではたくさんの種類があり、ヒレカツ丼もあればロースカツ丼もあり、さらにその上に目玉焼きが乗っていたり、様々なバリエーションでソースカツ丼を味わうことができました。とっても満足に味わうことができましたので、是非皆さんにもお勧めしたいお店です。
とんかつ味処 くら
福井県福井市北四ツ居1丁目1−8
0776-53-6586
二上観音堂のアクセス方法
今回私は車で訪問しましたが二上観音堂へは、JR大土呂駅から徒歩20分ほどで行くことができます。電車は1時間に1本程度あり、地方にしては比較的アクセスよく便利です。
感想
二上観音堂の思い出と言ったら何と言っても仏像リンクのメンバーの皆さんが境内に行ったら、わんさかいろんなところにいたこと。
個人的には誰かには会うだろうなと思っており2、3人くらいの人にお会いするかなと思っていたら、境内に行ってみると、その時にいた3分の1は仏像リンク関係の知り合いの方々ばかりで、十一面観音さんを前に同窓会のような雰囲気になっていました。


下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

地域タグ:福井県
【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう
新TV見仏記
地方仏を歩く|丸山尚一
【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア
図説 みちのく古仏紀行
■関東エリア
東京近郊仏像めぐり
■東海エリア
東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重
■関西エリア