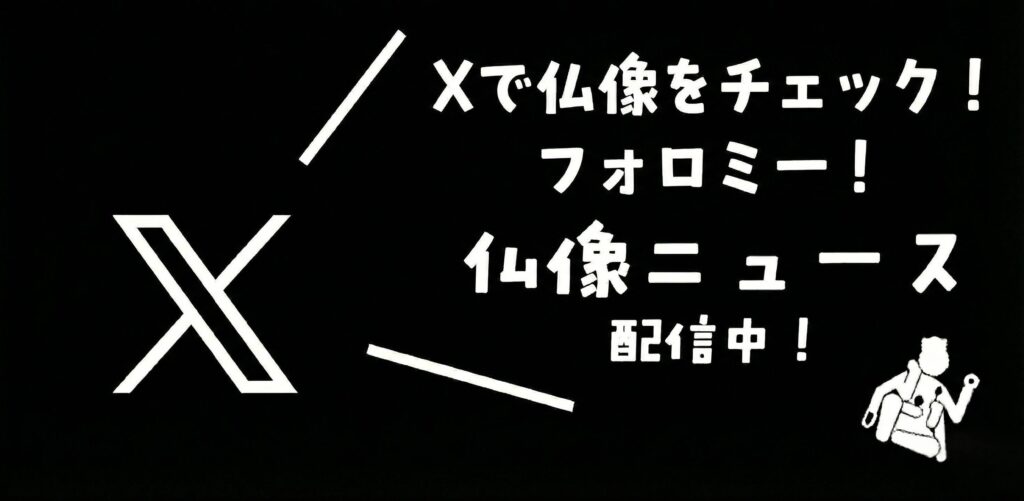【国宝仏像11体すべてを公開!】中尊寺金色堂建立900年記念展が東京国立博物館で開催

東京国立博物館で開催される建立900年 特別展「中尊寺金色堂」の内覧会へ行ってきました!
実は自分が大学時代に一緒に遊んだ友人の友人という人物が、この中尊寺のお寺の娘さんだったことが判明して、めちゃくちゃビックリした記憶がありました。なので過去中尊寺には何度か訪問したことがありましたが知人の実家訪問の感覚もあったり。
今回の展覧会ではズラーッとならぶ国宝級の仏像の数々。きらびやかな世界に没入することができ、まるでドラえもんのスモールライトを手に入れ、金色堂の内部へと足を踏み入れるような感覚!驚くほどの没入感が訪れます。展示されているのは、ほとんどが国宝級の品々。国宝の仏像に囲まれてうっとりしたい方にはぴったりの展覧会でした。
中尊寺展の紹介ぜひ楽しんで見ていってください!
中尊寺金色堂展に行ってきました。
国宝の仏像を間近で観ることができたり、
金泥で塔の形に写経された金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅がとても素晴らしかったです。平泉にもいつか行ってみたいです。 pic.twitter.com/6sbPbjrBNt
— 狐のお宿 (@kitsunenooyado) January 24, 2024
トーハクこと東京国立博物館の中尊寺金色堂展を観てきました。
漆黒の室内に金色がキラキラしてました!
実際に中尊寺金色堂行った時は、阿弥陀如来様は遠くに鎮座してるのですが、トーハクでは間近で見る事ができます!#トーハク #東京国立博物館 #中尊寺金色堂 pic.twitter.com/KFnriJGArU— フジ (@fwns7386) January 24, 2024

特別展「中尊寺金色堂」の開催場所は?

まず今回の特別展「中尊寺金色堂」は、東京国立博物館本館特別5室で開催されています。
この会場は以前にも「京都・南山城の仏像」や「空也上人と六波羅蜜寺」といった仏像の特別展を開催した舞台です。本館の正面から入って右側から入場します。
特別展「中尊寺金色堂」の注目のポイント!

中尊寺金色堂、世界遺産に指定されている中尊寺は日本人だけでなく世界にも知られる建築です。これは1124年に藤原清衡が建てた東北で一番古い建物ですが、2024年に900年の節目を迎えることになり、それを記念して今回の特別展が開催されることになったようです。
今回の展覧会の目玉は中尊寺金色堂の中央壇の国宝の仏像11体が勢揃いしているのです!
金色堂の中には3つの須弥壇があって、それぞれの中には今でも清原家の3代当主たちの遺体が納められた棺があるのです。特に注目は、中央壇に眠る、金色堂を建てた藤原清衡さんご本人の壇。この展覧会では、藤原清衡が眠る中央壇にまつられる仏像11体がずらーっと展示されているのです。さらに、金色堂をきらびやかに輝かせてきた豪華な工芸品も多数展示されています。
そして、もう1つの見どころが超高精細な8KCGで金色堂が目の前に!幅約7メートルの巨大ディスプレイで、金色堂とその内部を実物大で見ることができるんです。これはねぇ、わかりやすく言うと、ドラえもんのスモールライトで小さくなって、金色堂の内部に入ったような感覚になるんです!
 NHK/東京国立博物館/文化財活用センター/中尊寺
NHK/東京国立博物館/文化財活用センター/中尊寺900年もの間、黄金に輝く空間で祈りがささげられてきた仏像たちが迫力ある美しい映像で、自分自身が金色堂の内部に入ったかのような体験するのは、本当に面白い体験でした!
中尊寺の歴史

ここで中尊寺とは?をまずわかったうえで訪問できるよう簡単に中尊寺の歴史をまとめていきたいと思います!
まず、中尊寺は、寺伝では慈覚大師円仁さんって言われているんですが、実際のところは平安時代に奥州藤原氏の初代、藤原清衡さんが建てたと考えたほうがしっくり来ます。清衡さん、本当に色々な戦い(前九年の役、後三年の役)を乗り越えて、東北のボスになったんです。
たくさんの死傷者を出した結果、藤原清衡さんは戦いの傷跡を癒すために仏教に目を向けたんです。
さて、この清衡さん、とんでもなく大胆なことをやったんですね。白河の関から外浜まで、めっちゃ長い道のりに塔婆をバンバン建てて、金色の阿弥陀仏の絵をちりばめたんです。これって、もう「ここは藤原の地域だよ!」って宣言しつつ、「仏さま、ここを平和にしてね」って願ってるようなもの。そして、中尊寺はその道のド真ん中にあるんです。
その名前、「中尊」には、「東北の中心にある寺」っていう意味が込められているんです。
でもね、時が流れて、鎌倉時代になると中尊寺、ちょっと衰退しちゃったりして。さらに南北朝時代の大火災で、多くの建物がなくなってしまいました。でも金色堂だけは今でも当時の姿を残してくれているのです。
【平安時代前期】
850年、慈覚大師が手がけた中尊寺が爆誕!(諸説あり)
【平安時代後期(奥州藤原氏時代)】
1105年、奥州藤原氏の初代ボス、藤原清衡が平泉に新居を構え、中尊寺で建築ラッシュを起こしました。その中で1124年、華麗な金色堂が誕生!奥州藤原氏の元で、仏教文化がめきめき花咲いた時代です。
【鎌倉時代】
1189年、奥州藤原氏、滅亡。でも、中尊寺は一時の衰退の後、1213年に鎌倉幕府が修復に乗り出し、また盛り上がりを見せます。
【江戸時代】
仙台伊達藩の後押しのもと、中尊寺は建築物をどんどんと整備。参道の杉並木もこの時代の自然演出によるものです。
【近現代】
1929年、金色堂はなんと文化財保護法による国宝建造物第1号に認定!そして1979年には特別史跡、2011年には世界遺産に。今も中尊寺は、日本の歴史と文化を語る大切な証人として存在しています。
特別展「中尊寺金色堂」のおもな仏像

では、ここから仏像リンクらしく、今回の展覧会で展示されている仏像について紹介していきたいと思います!
国宝・阿弥陀如来坐像(12世紀)

中尊寺金色堂の阿弥陀如来像です。この展覧会の主役となる存在です!12世紀の平安時代に作られたこの像、なんと高さ62cm。小さくてもその存在感は絶大!中央の壇にドーンと鎮座していて、落ち着いた雰囲気で丸顔。でも、表情はちょっと厳しめって感じ。まるで藤原清衡さん御本人を象徴するような存在です。
 国宝 阿弥陀如来坐像(平安時代・12 世紀 岩手・中尊寺金色院蔵)
国宝 阿弥陀如来坐像(平安時代・12 世紀 岩手・中尊寺金色院蔵)
この仏像、京都の超一流の仏師が作ったと思われるんです。なんといっても、その滑らかな曲線と肉付き、本当に美しいんです。素材はヒノキ。職人技の「正中」という技法を使って作られているんですって。さらに後頭部の髪の刻み方や右肩にかかる衣を別材で作る点などが挙げられます。さすが、時代の最先端。技術の粋を集めた作品ですよね!
この像のスタイル、当時としてはかなり斬新。新しい流行を取り入れた奥州藤原氏のセンスの良さが光ります。京都の仏像と比べても全然遜色なし。むしろ、一歩先を行っているんじゃないかって思えるほど。この仏像があるおかげで、平泉の仏教文化がいかに豊かで先進的だったかがよくわかります。
国宝・観音菩薩立像・勢至菩薩立像(12世紀)

勢至菩薩立像と観音菩薩立像、中尊の阿弥陀如来像とともに「見た目も中身もピカイチ」な仏像たちです。まず、頭部がちょっと大きめで、表情はめちゃくちゃ穏やか。まるで見ているだけで「ほっ」と一息つくような、そんな優しい雰囲気を醸し出しています。
体のラインはまるでダンサーみたいにしなやか。衣の彫りはさりげなく、それでいて存在感バッチリ。金色堂を表すように全体が金色に輝いていて、見る人をうっとりと圧倒するほどの美しさです。
で、これが面白いんですけど、この像たち、中央の阿弥陀如来像といろいろ共通点があるんです。制作年代も1111年から1228年頃と、同じ時期。これは、きっと清衡さんが「ここは一気に作ってください!」って発願した阿弥陀三尊像として作られたんじゃないかと思われます。
京都の技術と比べても全然引けを取らないクオリティ。当時のトップクラスの仏師“円勢”周辺の仏師が関わっていたと思われます。京都で作ったのかな、でも材料のことを考えると、京都から仏像や仏師がやって来たのかも。でもとにもかくにも平泉にあった豊かな仏教文化の証拠であることは言えそうです。
国宝・地蔵菩薩立像(12世紀)

中尊寺金色堂の地蔵菩薩さんたちです!この6体の地蔵さんたち、阿弥陀如来像の両サイドにずらりと並んでいて、まるでお城にずらっとならんだ家来のよう。それぞれの像が、宝珠を持って、なんとも落ち着いた立ち姿。優しい雰囲気を感じさせます。
高さは64cm~62.8cmと、平安時代の12世紀に作られたことがわかっています。
六地蔵信仰は、当時なくなった人の追善供養のために造像されることが多かったため、金色堂の構成が当初の計画によるものなのか、清衡の没後に追加されたものなのかについては意見が分かれています。しかし、どちらにせよ、この六地蔵は金色堂の豊かな尊像構成の一部を形成しています。
これらの像はカツラ材で作られた可能性が高く、もともとは別の場所(金色堂内の西壇)に祀られていたんじゃないかなと思われます。台座と光背は、昭和時代の大修理時に補作されていますが、それもまた歴史の一部ですよね。
国宝・二天立像(12世紀)

次に二天像こと持国天像と増長天をご紹介!まずは持国天像、ほかの像と同じくこの像は平安時代の12世紀の作。高さは66.3cmで、木造漆箔彩色像です。この像の一番の見どころはその姿勢。目をいからせながら口を結び、左手を高く上げて、右手をバシッと振り下ろしているんです。まるで、何か大事なメッセージを伝えようとしているかのような迫力です。

次に、増長天像の話。こちらもまた平安時代の12世紀の作で、高さは65.0cm。こちらも木造漆箔彩色で、とってもカッコイイんです。口は開いていて、右手を高く上げ、左手を振り下ろすスタイル。まるでダンスしているような躍動感がありますね。
この像、頭部や持物、邪鬼が後から追加されているんですよ。もともとはもっと違ったスタイルだったかもしれません。
TMレボリューションのように風を受けまくるなかでダンサブルなスタイル。見るからに躍動感がありますよね!それと同時にとってもアーティスティック。平安時代の人たちのセンスの良さを感じさせてくれます。
藤原清衡さんの木棺も展示!金箔押木棺

中尊寺金色堂がただのお寺・お堂ではない明確な違いを最後に抑えましょう。それは中尊寺金色堂は現在も藤原清衡さんをはじめとした藤原四代の“お墓”でもあること。それを証明するものがこちらの木棺です。
総体を黒漆塗りで仕上げられ、内外に金箔を押した漆箔の技法で金色に輝かせています。このデザインは、釈迦が入滅したとされる金棺を模したものと考えられています。
この棺、ただの棺ではありません。現在も金色堂内に眠る、奥州藤原氏の初代、清衡さんの遺体が納められていた棺なんです。中央壇の下にドーンと鎮座する、キラキラ輝く金色の棺。これが、まさに黒漆塗りに金箔をびっしりと押した棺なんです。なんてゴージャス!
しかもね、この棺、底には謎の穴があいているんです。実はこれ、遺体の体液を外に出すための工夫だったんですよ。昔の人の知恵には驚かされます。
清衡さんのご遺体は、一部がミイラ化していて、他は白骨化していたそうです。そして、この棺の中には金塊や枕、衣類、刀類、念珠など、もう色々な副葬品がギュッと詰まっていたんです。これらの副葬品は、当時の奥州藤原氏の地位や文化を示す重要な資料となっています。
特別展「中尊寺金色堂」のグッズ

特別展「中尊寺金色堂」のグッズを紹介していきましょう!まず目玉は、カラフルな図録です。この図録、ただの図録じゃありません。展示作品50件をバッチリフルカラーで収録していて、ところどころに金の加工が!ページをめくるたびに中尊寺の美しさがドーンと飛び込んでくるんです!国宝仏像の精巧なディテールもバッチリ、価格は2,800円(税込)。

次に、超キュートな邪鬼ぬいぐるみ!これは、3,850円(税込)。国宝の持国天立像に踏みつけられてる邪鬼をモデルにしたなんともユニークなデザイン。クッションとしても使えるから、お部屋のアクセントにぴったりですね!
そして、金箔缶マグネット。これがあれば、毎日の冷蔵庫開け閉めが楽しくなりそう!金箔の輝きが、キッチンを華やかにしてくれるはずです。
ほかにも金色堂にちなんだグッズが色々!
以上、中尊寺金色堂の特別展のグッズたち。これらのアイテムで、特別展の思い出をいつまでも。展覧会が終わったらグッズ売り場へGO!
東博で始まった中尊寺金色堂展。小ぶりながらも現地では遠くからしか見られない国宝の阿弥陀如来像や観音菩薩像が本当に目と鼻の先で見られる最高の内容なので絶対行ったほうがいいよ。たぶんこれ逃したらもう機会ないんと違うかな。あと図録は絶対買うべし。これで2800円という破格の安さ pic.twitter.com/UVRHIbAfHK
— オース (@aPIpTDqpx4hfSuo) January 24, 2024
中尊寺展の混雑状況
混雑状況は展覧会のツイッターで最新状況が発信される可能性があります
中尊寺展のチケット
チケットの各料金はこちらです
・当日券|前売り券
一般 1,600円(一般前売 1,400円)
大学生 900円(大学生前売 700円)
高校生 600円(高校生前売 500円)
展覧会の会期、料金、場所、など
展覧会名 | 建立900年 特別展「中尊寺金色堂」 |
会期 | 2024年1月23日(火)~4月14日(日) |
会場 | 東京国立博物館 本館特別5室 |
休館日 | 月曜日、2月13日(火) (注)ただし、2月12日(月・休)、3月25日(月)は開館 |
拝観時間 | 9時30分~17時00分(入館は閉館の30分前まで) |
拝観料金 | 当日券 一般 1,600円 大学生 900円 高校生 600円 |
.

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう
新TV見仏記
地方仏を歩く|丸山尚一
【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア
図説 みちのく古仏紀行
■関東エリア
東京近郊仏像めぐり
■東海エリア
東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重
■関西エリア