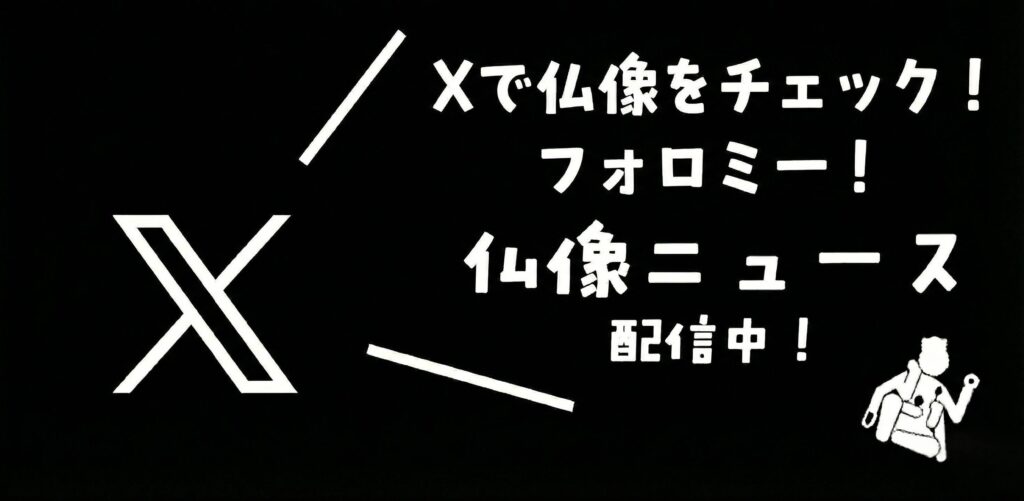【しずおかの古仏たち】静岡市歴史博物館で静岡市の仏像が大集合!見どころ徹底解説(2025年秋)

いよいよ、この秋すごい企画展が始まるということで、静岡駅へ行ってまいりました!
静岡での展覧会といえば、浜松市美術館や伊豆の上原美術館などが有名ですが、今回は静岡駅のすぐ近くで、めちゃくちゃ大きな仏像の展覧会が開催されるとのことで、東京から静岡駅に降り立ちました。
展覧会の前に、サウナの聖地として知られる「サウナしきじ」に立ち寄り、心身ともにスッキリ。そのあと静岡駅近くで新鮮なマグロ丼をいただき、心も体もお腹も満たされた状態で静岡市歴史博物館へ向かいました。

この博物館は、かつて駿府城があった場所に建てられていて、立派な石垣に囲まれた城跡の中にあります。そんな歴史ある地で開催されるのが、今回の待望の企画展「しずおかの古仏たち」。静岡市内のさまざまなお寺で大切に守られてきた仏像や、仏教信仰を物語る歴史資料を一挙に紹介する、まさに“静岡市の仏像の祭典”ともいえる企画展なんです。 アクセスも抜群で、静岡駅から徒歩でも訪れることができる便利な立地。 それではさっそく、「しずおかの古仏たち」展の見どころをチェックしていきましょう!
静岡市内のスゴイ古仏たちが集結!「しずおかの古仏たち」展の見どころはココ!
この展覧会、静岡市内の寺院でずーっと大切にされてきた仏像や貴重な品々が、なんと約45点も集まるってるんです! 静岡といえば静岡東部に位置する願成就院や伊豆ならんだの里 河津平安の仏像展示館など伊豆半島の仏像のイメージを持つ人も多いかもしれませんが、この展示がされる静岡市内にも数多くの仏像がいらっしゃるんです。静岡といえば海沿いの仏像をイメージする人も多いかもしませんが、この静岡市周辺では山間にも素敵な仏像がいらっします。そんな大好物な静岡の地方仏たち。その土地で生まれて、地域の人たちにずーっと愛されてきた仏さまたちが一堂に会する機会、これはめちゃくちゃありがたいチャンスです!
展示される仏像の中には、新光明寺の「木造阿弥陀如来立像」のような国指定の重要文化財が来ちゃうんです!新光明寺 といえば静岡駅前のビルのなかにあるお寺。エレベーターを降りてこちらの展覧会にやってきてくれるんです。
まだまだすごい仏像があって霊山寺(れいざんじ)の高さ2メートルを超える県指定文化財「木造金剛力士立像」(仁王像)が、3年間の修復を終えて寺外で初めて公開されます。この大迫力の仁王像は、いつもの3階展示室だけじゃなくて、なんと1階の遺構エリアにどーん!と特別展示されるんです。通常の博物館ではなく博物館全体を使ったかなり大規模な展示会なんです。 博物館の本気度を感じます…!
他にも、久能寺(くのうじ)や「幻の寺」なんて呼ばれる建穂寺(たきょうじ)の仏像たちも来ていて、 静岡の仏像の世界って、知れば知るほど奥が深そう。その魅力を深堀りしていきますね。
静岡の仏像ハイライト!修復完了の仁王像と快慶様式の阿弥陀如来
今回の展示、たくさんの仏像が来るんだけど、中でも「これはスゴイ仏像!」っていう2大スター仏像はこちら!
【お寺の外では初公開!】高さ2m超 にびっくり!霊山寺「木造金剛力士立像」(仁王像)

まずは静岡県指定文化財である霊山寺の「木造金剛力士立像」つまり仁王像! 2体は、その像高が2メートルを超える大迫力の仁王像です。この阿形(あぎょう:口を開いた像)と吽形(うんぎょう:口を閉じた像)の一対の像は、平安時代から鎌倉時代に作られたんじゃないかなって言われてるすごい大迫力の仁王像でした。
そしてこの日びっくりな出会い!この仁王像の前でこの仁王像を修復した吉備文化財修復所牧野隆夫さんにばったりお会いしました!牧野さんのお話ではこの仁王像、長い間、雨風にさらされてボロボロの状態で、自分で立つことすら難しくなっていたそう…。それを、3年もかけて丁寧に修復したんです。今回の修理で、弱っていた脚をしっかり強くして、目は後から入れられたガラス玉じゃなくて、もともとの木彫りの状態に戻しているんです。これによって本来の姿に近づきました。で、ぎょえーっと思った修復の裏話。なんと仁王像を解体したら、脚の中から大量のドロバチの巣が見つかったそう、自分の身体をハチさんの寝床に提供していたまさに体を張った仁王像だったようです。これは修復した牧野さんたちはさぞかし大変だったろうな。ただそのおかげもあってか台座から「江戸時代に駿府の職人さんが直しました」っていう墨書のメモ書きが出てきたそうです。
そんな修復が終わったばかりの仁王像が、お寺の門に帰る前に、特別にこの展覧会でお披露目されるんです。お寺の外で公開されるのは、これが初めて!1階の遺構エリアでお会いできます!
【国重文!】慶派仏師のDNAを受け継ぐ、新光明寺の阿弥陀如来さま

もうひとりのスターが、新光明寺の「木造阿弥陀如来立像」です。 そしてこちらの阿弥陀如来は国指定重要文化財(国重文)です。静岡市歴史博物館で国重文の仏像が展示されるのは、これが初めてのことなんだとか。
この仏像が作られたのは、鎌倉時代。キリッとした若々しいお顔立ちと、力強い雰囲気が魅力的で、 鎌倉時代のスター仏師 快慶(かいけい)の様式を強く受け継ぐ作品とされています。特に、シュッとしたお顔立ちや体のラインの美しさは、快慶の初期の傑作とされる奈良・西方寺の阿弥陀如来像にきわめて近いと評価されています。
そしてX線でじっくり中を覗いてみたら、なんと胸のあたりに、木でできた小さな五輪塔(ごりんとう:地水火風空の五大要素を象徴する塔) が納められていることがわかったんだそう! この阿弥陀さまも、数年前に修復が終わったばかり。

そして、修復後にお寺の外でお目にかかれるのは、今回の企画展が初めてのチャンスなんです。
展示の構成:静岡の寺院を巡る4つの物語
本展覧会は、4つの章に分かれていて、静岡のいろんなお寺の歴史を、まるで旅するみたいに楽しめる構成になってるんです。静岡の仏教の世界って奥深いんだなぁって感じるその構成を紹介していきます。
1. 久遠の歴史を伝える久能寺と鉄舟禅寺の仏像(第1章)
最初は、久能寺(くのうじ)というお寺の紹介からスタート!この久能寺、昔は有度山(うどやま)にあって、お坊さんの部屋が300以上もあったというから、ものすごく大きなお寺だったようです!海が見える場所で、芸能も盛んだったなんて、なんだか華やかな光景が目に浮かびます。
でも、戦国時代に駿河を支配した武田信玄の命令で清水の町なかにお引越しさせられたり、明治時代には一度なくなってしまったり…かなり波乱万丈な歴史を持っているんです。
それを幕末の傑物、山岡鉄舟が「こんなに素晴らしいお寺がなくなるのは惜しい!」と復活させたのが、現在の鉄舟禅寺(てっしゅうぜんじ)なのだとか。
ここで会えるのが、久能寺に古くから伝わる「木造文殊菩薩坐像」です。平安時代らしいふっくらしたお顔立ちの中に、どこか鎌倉時代らしいキリッとした雰囲気もあって、そのバランスが絶妙なんです。そして、この仏像で一番驚くのが、中から見つかったもの。

なんと、知恵の仏さま・文殊菩薩を表す文字(梵字というインドの文字です)が、1万個もびっしりと書かれた「大聖文殊種字一万躰巻子」(だいしょうもんじゅしゅじいちまんたいかんす) という巻物が納められていたんです!知恵の菩薩である文殊菩薩が厚く信仰されていたことを証明する貴重な資料です!
ちなみに、鉄舟禅寺には現在、京都国立博物館に寄託されている平安時代の雰囲気漂う千手観音像もお祀りされています。数十年前に一度お会いしましたが、いつかまたお会いしたい仏像です。残念ながら今回は展示されていません。

他にも、鉄舟禅寺に祀られる菩薩坐像(鎌倉時代前期の慶派の雰囲気!)も展示されていました。こちらは残念ながら頭部のみが当時のもので、それ以外は新しく作られたものとのことでしたが、鋭い眼光と豊かな頭髪の表現が非常に印象に残りました。

また、現在は一乗寺に祀られる宝冠阿弥陀如来坐像も。もともとは同じく久能山に祀られていた仏像だそうで、私も以前お寺でお会いしていますが、衣紋の表現がとても見事で、見とれてしまうほどの美しさでした。

2. 観音の霊場、霊山寺の守護神たち(第2章)
次の舞台は、清水の山あいにある観音さまの聖地、霊山寺(れいざんじ)です。 ここには、ご本尊の千手観音さまを守る「二十八部衆」っていう、いわばガードマンチームのような仏さまたちがいらっしゃいます。仏像好きの方は、京都・三十三間堂のずらーっと並ぶ千手観音の手前に並ぶ存在として有名ですよね。 今回はその中から、選抜メンバー8体が登場します!

そのなかの1体をご紹介します。県指定文化財の「木造伝婆藪仙人立像(もくぞうでんばすせんにんりゅうぞう)」です。

婆藪仙人(ばすせんにん)は、痩せたおどろおどろしい、ちょっとコワモテな表情が印象的ですが、こちらの仏像はちょっとコミカルな「意地悪ばあさん」っていうような印象でした(笑)
台座には、鎌倉、室町、江戸と、何度も修理されてきた記録が残っているらしいんです。それだけ長い間、地元の人たちに大切にされ、信仰されてきた証なんでしょうね。
霊山寺からは他にも複数体の仏像が展示されています。個人的には、二十八部衆のうちの帝釈天が非常に頭部が大きく個性的だったのも、今回の展覧会訪問の中で印象に残りました。

4. 地域で守り継がれた「幻の寺:建穂寺」の仏像群(第4章)

最後は、「駿河の高野山」と称されるほど隆盛を極めた「幻の寺」 、建穂寺(たきょうじ)です。
このお寺、昔は「駿河の高野山」って呼ばれるくらい、ものすごく栄えていた大寺院だったらしいんです。徳川家康からも特別扱いされるほどだったとか。
でも、明治時代の初めの悪しきムーブメント、廃仏毀釈によって仏教がピンチになったり、その後の火事で建物が全部焼けてしまったりして、お寺そのものがなくなってしまい、ついには廃寺となってしまいました。
しかし建物は燃えちゃったけど、仏さまたちの多くは、地元の人たちが火の中から命がけで運び出して、焼けるのを免れたんだそう! これは泣けます、、。
地元の方の必死の救護活動によって今も約60体の仏像が残っています。でもお坊さんや檀家さんがいないから、地域の人たち、特に建穂自治会のみなさんで大切に守り継いでいるんです。私も10年ほど前に訪問しましたが、地元の人から直接案内いただいて、仏さまを大切にしていきたい地元の方の思いを直接感じました。

今回は、その仏像群の中から6体が登場します。 鎌倉時代の慶派の作と推定される「不動明王立像」(県指定文化財)など、力強い仏像を見ることができます。この不動明王立像は、像高80センチのヒノキ材で造られ、13世紀後半の作とされています。

また、 桃山時代に作られた一体の「地蔵菩薩像」も展示されています。こちらはかつてすごく傷んでしまっていたんだそう。でも、お寺じゃないから修復のためのお金がない…。そこで地域の人たちが立ち上がり、2016年にクラウドファンディングを立ち上げて、修復費を集めることに成功しました。
今でこそ仏像やお寺の修復でクラファンを利用することは比較的ポピュラーになりましたが、地域の人たちが自分たちの手で仏さまを守るためにクラファンを使った、日本で初めてのケースとなったそうです。
静岡市歴史博物館へのアクセス・観覧料

最後に、企画展「しずおかの古仏たち」を訪問される皆様へ、会期やアクセス、観覧料、図録情報についてご案内いたします。
まずは、開催期間や場所といった基本情報です。
会期: 2025年10月25日(土)~ 12月7日(日) 会期は41日間と限られていますので、お見逃しのないよう、お早めに計画を立てるのがおすすめです。
会場: 静岡市歴史博物館(静岡市葵区追手町4番16号) 通常の3階展示室に加え、迫力ある仁王像が展示される1階の遺構エリアも使用した、規模を拡大しての特別展となっています。
開館時間: 9:00~18:00 (展示室への入場は閉館30分前の17:30までです)
休館日: 月曜日 ただし、祝日と重なる場合は開館し、翌平日が休館になるなど変動があります。 10月27日(月)、11月10日(月)、25日(火)は臨時で開館するようですので、普段月曜日がお休みの方には嬉しいポイントですね。訪問前には公式サイトで確認すると確実です。
観覧料について 企画展のみを観覧する場合の料金はこちらです。
【観覧料(企画展のみ)】
| 対象 | 個人 | 団体(20人以上) |
| 一般 | 600円 | 480円 |
| 高校生・大学生、静岡市内居住の70歳以上 | 420円 | 330円 |
| 小学生・中学生 | 150円 | 120円 |
- 静岡市内居住・通学の小中学生、未就学児は無料です。
- 常設の基本展示も一緒に観覧できるお得なセット料金(一般1,200円など)も用意されています。
- 各種割引の対象となる方は、学生証や身分証明書などをお忘れなく。
仏像と関連資料を網羅したフルカラー図録

展示された仏像や地域ゆかりの資料を一冊にまとめた、充実の公式図録が刊行されます。
販売は企画展の開幕日、10月25日(土)からスタート。
図録はA4サイズ・全72ページのフルカラーで、価格は1,200円。
博物館のミュージアムショップのほか、WEBでも購入できます。
写真も美しく、仏像の細部や修復の記録、各寺院の歴史などが丁寧に紹介されています。
「会場で見逃したあの仏さまをもう一度見たい」という方にもぴったりの内容。
訪問を終えての感想
なつかしい仏像・新しく出会った仏像のオンパレード。静岡市の仏像たちの奥深さをやはり感じましたね。 個人的には三重亀山の慈恩寺像のような厳しい雰囲気の如来さんがとっても好きで、快慶スタイルの新光明寺の阿弥陀如来さんはめっちゃいいですね。 地方にありながら、都の仏師が作ったかのような、若々しくて力強いオーラを放っていました。
建穂寺もエピソード含めめっちゃ素晴らしいですよね、廃仏毀釈や火災という困難を乗り越え、さらにはクラウドファンディングという現代的な方法で、地域の人たちが自分たちの手で守り継いできたというエピソード。 文化財が「地域の宝物」として今も大切にされているんだなあって思います。文化財を守る難しさもあればそれを守っていく人々の創意工夫を垣間見えてこれからの仏像のあり方を考えさせられる展示です。ぜひお近くの方もそうでない方も仏像好きな方であればぜひ行ってみてください!